日本歴史上、田沼意次ほど評判の悪い人物はいない。とくに戦前は、弓削道鏡・足利尊氏とともに、「日本歴史の三悪人」とまで言われたものである。弓削道鏡と足利尊氏は皇室にたいする姿勢からであるが、田沼意次の場合は賄賂を好み、賄賂によって政治を左右したという政治姿勢にたいするものであるだけに、その悪評はのちのちまで生き残っているありさまである。
第9代将軍徳川家重の小姓となり、第10代将軍家治の側用人・老中へと昇進した田沼意次は、財政・開発事業などの面で多角的かつ革新的な幕政を展開。しかし、度重なる飢饉(ききん)や大火、さらに浅間山の大噴火といった未曽有の大災害に見舞われ、在任中の運営は綱渡り状態だった。さらに、武家社会では身分の低い地位から異例の出世を果たしたことで、周囲に敵も多く、後世にまで執拗にささやかれる「賄賂政治家」という悪評の原因ともなった……。
こう聞くと、たとえば伊達藩家臣・原田甲斐の従来のイメージを覆した山本周五郎の小説『樅ノ木は残った』のような印象を抱くかもしれない。しかし、本書はいわゆる評伝ではない。謎多き稀代の政治家・田沼意次の存在をあくまで作品の中心に据えながら、彼とかかわった人物、彼がかかわった出来事、のちに彼のマイナスイメージが作り上げられていった過程などを丹念に調べ上げることによって、タイトルどおり、田沼意次という人物が生きた時代の様相を浮き彫りにしていく。
本書のエピローグで、著者はこんなことも語っている。
私は本書にとりかかる前までは、田沼意次の人間についても十分書きこんでみたいと思っていた。しかし人間について書くには、歴史は小説の場合にくらべて著しく条件が劣っている。信頼できる史料がなければ一行たりとも書けないからである。したがって私は準備段階でかなり丹念に史料を探ってみた。その結果私にわかったことは、田沼意次については個的な史料はもちろんのこと、彼をとりまく根本的史料もほとんどといってよいほど、残っていないということであった。
この劇的なエピローグをのぞいて、本書は田沼意次本人の肖像というより、彼を取り巻く時代状況や人間関係、いつの世も変わらない権力闘争の醜さなどを炙り出していく。その独特の構成、語り口は、むしろ『べらぼう』効果で“時代そのものへの興味”が高まっている現代にはぴったりの内容かもしれない。
そして言うまでもなく、相次ぐ天災、不安定な国政、トップの地位に立ちながら四面楚歌に追い込まれる政治家といったシチュエーションは、2025年現在の日本の光景もまざまざと想起させる。本書が最初に刊行された1991年当時にはどのような「時代の要請」があり、それを著者がいかに鋭敏なアンテナでキャッチしたかを分析する、近世史研究者の村和明氏による解説も必読だ。
そんな特殊な性質をもつゆえか、本書でひときわ印象に残るのは、田沼意次の功績よりも、道半ばで頓挫した事業や、失脚への道といった部分である。彼に相当な精神的ダメージを負わせたであろう息子・田沼意知の殺害(暗殺)事件の顛末も、執拗なほどディテール豊かに描かれる。
天明四(一七八四)年三月二十四日のことである。田沼意次の子意知(おきとも)が、一日の役務を終って同僚の若年寄たちと御用部屋から新番所前廊下を通って御殿を退出しようとしていた時のことである。新番組の佐野善左衛門政言(まさこと)は白刃をふりかざして走りでてきて、意知の肩さきに切りつけた。意知は腰の刀で防ごうとしたが間に合わぬので、桔梗の間の方に逃げだしたが倒れたところを股を三寸五、六分ほど切られ、刃は骨まで達した。
田沼意次を刺殺して権力を奪回しようとまで思いつめていた政敵松平定信が、天明五(一七八五)年十二月一日に溜之間詰になって、江戸城の一角に橋頭堡(きょうとうほ)を確保した。溜之間というのは江戸城中奥黒書院脇にあり、臣下に与えられた最高の席で幕府の政治顧問の詰所という性格をもっている。翌天明六年八月十五日には田沼意次のうしろだてになっていた将軍家治が発病すると、意次も病気という理由で老中職を罷免された。そして田沼意次によってすすめられていた印旛沼(いんばぬま)の開発、蝦夷地開発の計画などが、つぎつぎに中止となり、同年十月二十八日にはついに蝦夷地調査も全面的に中止ということになってしまった。
(中略)
天明六年十月、意次は隠居を命ぜられ、領地のうち二万石を没収される。この間将軍家治が死亡、家斉が一一代将軍となり、同七年六月松平定信が老中になり、その首座となると、田沼意次をめぐる情勢は一段と悪くなり、同年十月にはさらに二万七〇〇〇石を取り上げられたうえ、城地没収、下屋敷に蟄居謹慎するようにという追討ちをかけられた。なお田沼家の家督は孫の竜助に許され、陸奥国の内で一万石が与えられた。わずかに大名としての面目は保ったわけである。
『べらぼう』ファンには、最終章の「田沼時代の社会」がいちばん楽しいかもしれない。同時代を生きた杉田玄白、大田南畝(蜀山人)といった文化人が続々登場し、著者が「江戸時代でもっとも幅の広い豊かな社会」と語る宝暦・天明期の江戸文化の片鱗を感じ取れる。一方、著者は杉田玄白の優れた観察眼を通して、この時代が「天変地異、人災凶災が打ち続くなか、一揆が頻発し流言蜚語(りゅうげんひご)が横行した、安定を欠く時代」でもあったことを伝える。
なかでも時代のターニングポイントともいえる出来事だったのが、天明三年(1783年)に起きた浅間山大噴火である。本書でも当時の逸話が詳しく語られる。著者はこのときすでに『天明三年浅間大噴火 日本のポンペイ鎌原村発掘』(1986年、角川選書刊)を発表しており、のちに講談社学術文庫『天明の浅間山大噴火 日本のポンペイ鎌原村発掘』として改題・再刊された(ここでもレビュー済)。こちらも併せて読むと面白いはずだ。
とすると、この噴火の三年後におこる田沼意次の没落、松平定信政権の登場も、杉田玄白が「若し今度の騒動なくば御政治は改るまじきなど申す人も侍りき」(『後見草』)と書いているように、天明の飢饉を契機として群発する一揆、打ちこわしにその決定的な要因があるので、「春秋の筆法」をもってすれば、天明の浅間山大噴火は、田沼意次を失脚させて松平定信政権を生み、フランス大革命を誘発してマリー・アントワネットをギロチンにかけた、ということになる。

 レビュー
レビュー


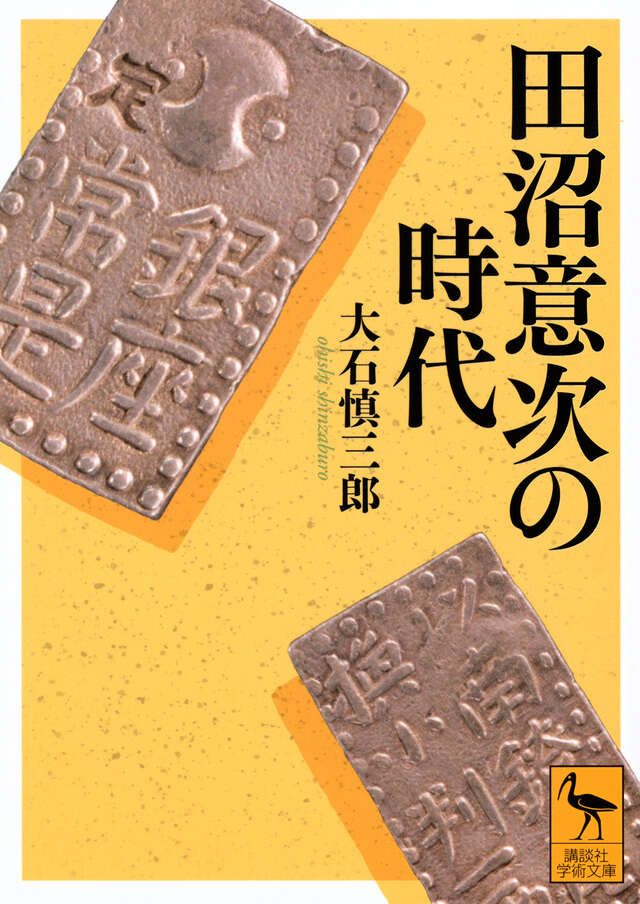








 特集
特集

