徴兵制の導入からして、外敵に備える制度というより、まずは国内をまとめるための“技術”であったという事実が見えてくる。教室で習った「国民皆兵」の標語が、生活と統治の接点でどう機能したのかが腑に落ちるにつれ、国防は外と内が二重に縫い合わさった営みだとわかってくる。「国防が単なる外敵防衛ではなく、国をまとめる技術でもあった」と素直に感じた。
帝国期に進むと、満洲の鉄や石炭といった資源の論理がむき出しになり、陸海軍の戦略文化の齟齬が火花を散らす。石原莞爾らの「殲滅戦」論は、敵国民そのものを目標化する思想の冷たさを露わにする。
総力戦の章では空気がさらに重くなっている。制度が日常の隅々まで伸び、相互監視が当たり前になると、人は言葉や表情まで用心深くなる。だから、婦人や子供たちに後方で頑張らせることの重要さが浮き彫りになる。反戦のささやきをさせないための相互監視の仕組みだったのだと。
そして太平洋戦争の降伏への議論では、国体護持という抽象が、現場の命より前に置かれてしまう瞬間が描かれている。政治の体裁が優先されてしまう、その冷ややかな事実が胸に残った。あの時々で“最適解”はあったのに、組織の論理や組織間の綱引きに呑まれ、歯車は望まぬ方角へ容易に転がってしまう。社会人なら覚えがある種類の“どうしようもなさ”が、安全保障のスケールで起きると被害は桁違いだ。
そして戦後の日本は“基地国家”という独特の生存方式を選んでいる。理想としての平和国家と、同盟・基地への依存という現実が突きつけられている構図である。ここを読んでいると、理想と現実のズレをなあなあにして見過ごしていくほど、将来の選択肢は細くなってしまうと感じた。さらに冷戦後は、災害・テロ・サイバーテロの領域が安全保障の中心になってくる。「何を守るのか」の答えが広がれば広がるほど、政治判断の難度は跳ね上がる。これが現代の危うさなのだろう。
そして今現在。台湾有事をめぐる議論が熱を帯びるたび、歴史は問い返してくる。「誰を、何から、どうやって守るのか」。外の抑止だけでは設計は完成しない。内側の制度、情報、避難、生活——暮らしの側からも設計し直さない限り、歴史は簡単に繰り返してしまう。経緯を人は忘れてしまうし隠蔽もしてしまうから。
結局のところ、国防という言葉は“外”だけでは完結しない。外と内、理想と現実、制度と生活。その三つ巴を意識できたとき、国防はようやく私たちの日常の日本語になる。結論を急がず、まず座標軸を合わせる。本書は、そのシンプルでいちばん難しい作業を静かに手伝ってくれる。書かれている物事が重い内容にもかかわらず軽く読めるのに、読み終えると自分の街の地図を広げたくなる。まずはハザードマップから。停電や通信障害、デマの連鎖といった身近な脆弱性まで連想が伸びていくのは、この本が「国防=生活設計」という視点を自然に呼び起こすからだ。
そしてもう一点、この本の誠実さを記しておきたい。敵味方の単純図式に逃げず、過去の選択を魔法の正解として棚上げすることもしない。勝敗や善悪の物語に切り縮めないからこそ、私たちは自分の足場で考えるしかなくなる。台湾有事も“流行語”として消費せず、長い時間の層の上に置き直して眺める。その距離感が心地よい。
項目ごとにまとめを記してくれているのもありがたい。決して押し付けるわけでもなく、議論のナビゲーションをしてくれるから、なんだかよくわからなかったな?という体験にならないのだ。
本書の読み方の提案の一つとしては、章末で一度ページを閉じ、自分の地域の地図に指を置いてみることだ。停電が長引いたら、通信が途絶えたら、どの道路がボトルネックになるのか。誰を、どこへ、どう運ぶのか。空理空論ではなく、生活の単位に落ちる問いに変換した瞬間、〈国防〉は自分の生活の一部になる。

 レビュー
レビュー


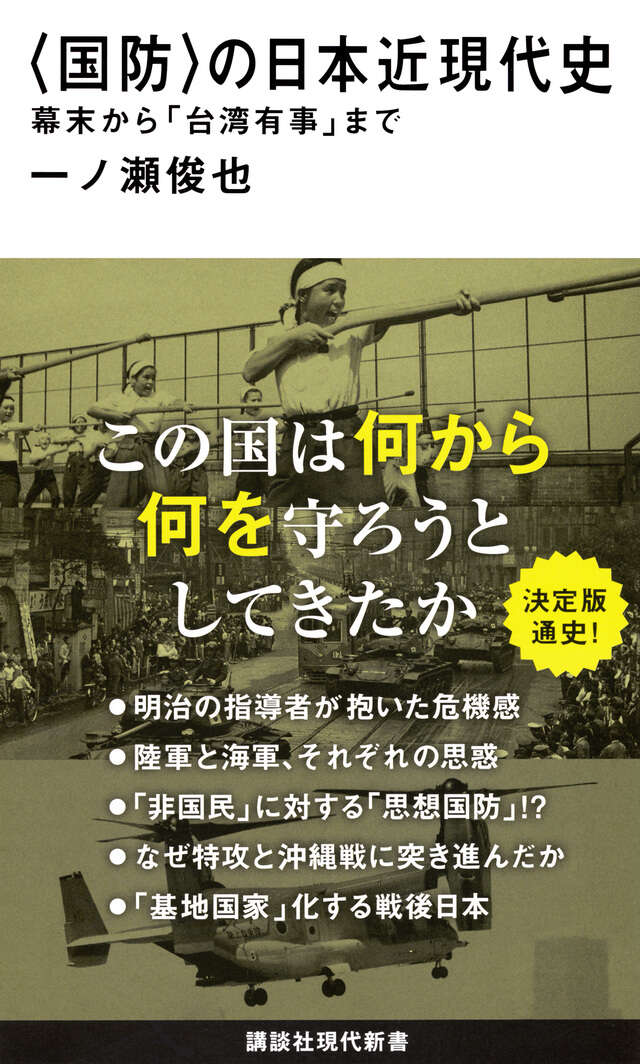










 特集
特集
