そのパワフルな言動、前のめりな行動力の源は何か。その原点にはどんな出会いや体験があったのか。興味を抱く読者は多いだろう。著者はこれまでの執筆活動と同じ力強い率直さで、その生い立ちと経歴を語っていく。
学生時代の私は、今のように物事の考え方が左寄りだったわけではない。ノンポリの学生だったし、「産経新聞でも読売新聞でも、どこでもいいから新聞社には入れればいいや」と思っていた。
2000年代の幕開けから始まる新人記者時代のエピソードには、早くも現在の姿を彷彿させる記述が(手痛い失敗談も含めて)散りばめられている。まだ前時代的な匂いを確実に残す日本社会の荒っぽいムードも感じさせつつ、現場でぐんぐん実力を身につけていく若き敏腕記者のドラマは、読者の興味をつかんで離さない。
弱小で部数も少ない東京新聞なのに、なぜ千葉支局で私がネタをたくさん拾えたのか。足を使ったからだ。県警幹部に食いこむためには、とにかく足を使って取材相手に信頼してもらうしかない。相手が早朝5時や6時に散歩したりジョギングする習慣があれば、朝から散歩やジョギングにつきあう。「こんな朝っぱらから朝駆けするとは、ずいぶん熱心で骨がある記者だな」と気に入ってもらい、「ウチで朝ご飯食べて帰れよ」と声をかけられるようになる。人間対人間の信頼関係を築き、心の襞(ひだ)に分け入るように話を聞き出すのだ。
取り調べを受けているときの私は、逮捕も起訴もされたわけではないのに、完全に被疑者・被告人の気持ちだった。「恥ずかしくないのか!」とずっと罵声を浴びせ続けられれば、人は誰だって心が折れ、やってもいないことを「私がやりました」と認めそうになる。自分がすごく悪いことをしてしまったかのように錯覚していく。「この建物から出た瞬間、誰かからマイクを向けられたらどうしよう」と恐れるぐらい、罪の意識を着せられていった。
(中略)
それまで私は、連日取り調べを受けている人に新聞記者としてズケズケ取材をしてきた。心理的、肉体的に限界まで追いこまれている彼ら彼女たちの心に、遠慮会釈なく踏みこんできたわけだ。自分が取り調べを受ける立場になって、初めて彼ら彼女らが味わってきた苦しさを実感した。
でも悔しいし腹が立つ。単身、副署長のもとを訪ねた。副署長室で話をしたら、話が他の人に丸聞こえになってしまう。「ちょっと裏で話してもいいですか」と言って、誰にも話が盗み聞きされない場所に移動した。そこで「ふざけんじゃねえよ! どういうつもりなんだよ!」とメチャクチャな剣幕で怒った。
副署長は、私がそんなに激怒するとは予想しなかったようだ。「本当に申し訳なかった。ついつい出来心でやってしまったことです。許していただきたい」と平身低頭、平謝りされた。幸いそれ以降、彼はセクハラ行為を二度とやらなくなった。それどころか、私を信頼して情報をたくさんくれるようになった。
本書には、著者の名を一躍知らしめた記者会見の数々についても、貴重な当事者目線で語られる。なかでも、いまだ冷めやらぬ怒りに満ちているのが、2023年10月2日のジャニーズ事務所会見だ。
このとき、著者はジャニーズ事務所からも、また本来は同志であるはずの報道陣からも、完全に“敵”と見なされた。ある意味、彼女が孤高のポジションを確立したエポックメイキングな瞬間だったといえるかもしれないが、当然、著者はこの日の記憶を「最悪の記者会見」と評する。
井ノ原氏の発言を受けて、最前列に座っていた芸能リポーターから大拍手が起きた。これには呆れてイスから転げ落ちそうになった。責任を問われるべき側が会見で「1社1問」「2時間のみ」と制限をかける。さらには特定の記者の挙手を無視することこそ理不尽なのに、記者側がそうした進行に異を唱えるどころか、会見の主催者に同調して拍手を送る。まるで全体主義国家の会議のようだ。いったい彼らは何のために記者会見に来ているのだろう。ジャニーズ事務所のプロパガンダでもやりたいのだろうか。
私はこれまで数えきれないほど記者会見に出てきたわけだが、これほどひどい記者会見は記憶にない。
いつもベランメエ調で記者会見に臨む麻生太郎氏は、威圧的でありつつも自由にしゃべる稀有な政治家だ。
(中略)
彼は「半径5メートルの麻生」と呼ばれていると聞いた。半径5メートル以内まで距離を詰めてきた政治部記者は、右(保守系)であろうが左(リベラル系)であろうは関係なく懐に抱きこんでいく。
銀座のクラブでお酒を飲みながらオフレコ懇談会をやっていたら、人間として政治家の情にほだされることだってあるだろう。だが、ジャーナリストはそこで厳しく一線を引かなければならない。政治家の懐に取りこまれたら終わりだ。半径5メートル以内まで食いこみながら、刺すべき場面ではペンで刺さなければならない。
トランプがしゃべる英語が極めてわかりやすいのも印象的だった。彼はインテリが好む難しいボキャブラリーを敢えて使わない。滑舌が良く、早口ではないため、英語がとても聴き取りやすい。日本人の私が聴いても、ストレスなくとてもわかりやすい英語だった。どうしゃべれば有権者の心に言葉が響くか、ナラティヴ(語り)を徹底的に研究しているのだろう。トランプは話芸の魔術師だと思った。
(中略)
自分がどう見られているか、己の姿を客観的に見ていることもよくわかった。この日はマイクの調子が悪かった。するとトランプはあからさまに不機嫌になり、スラングを連発してマイクのまずさを罵り始める。背が高いトランプに比して、マイクの位置が低すぎた。マイクスタンドをむしり取る大仰な仕草を見せると、聴衆はゲラゲラ笑って喜んだ。
最初に述べたとおり大部分は書き下ろしだが、第8章「こんな本を読んできた」は、東京新聞デジタルに連載された記事の再掲。著者による書評というかたちで、仕事や日常生活での所感がふんだんに織り交ぜられた文章は、実は最もパーソナルな読み物としての魅力に溢れているかもしれない。
以下は、おおたとしまさ『学校に染まるな! バカとルールの無限増殖』(ちくまプリマー新書)の彼女のレビューからの一部抜粋。この内容がどう書評と繋がるのかは、本書を読んで確かめていただきたい。
長女は中学生活に慣れてきて、最近は「学校の規則がうっとうしい」と愚痴をこぼすようになった。持ち物やら制服の着こなしやら、いろいろ細かいルールがあるらしい。「先生に抗議してみたら?」とアドバイスしたら、「ママみたいな人と思われたくない」と却下されてしまった。反抗期である。
それはさておき、既存のルールに疑問を持つことはいいことだ。そこには作った側の計算と思惑が潜んでいる。例えば記者会見でよくある「1社1人まで」「1人1問だけ」「関連質問なし」という規制。くだらないルールに思考停止で従うなんて、つまらない人生だよ、と長女には伝えたい。
自治体名は伏せておく。保守色がやや強いある地域で、ジェンダー格差や男女平等、雇用問題をテーマに講演をしたときのこと。事前に講演用のスライド資料約100枚を、講演を共催した団体と役所の担当者に渡していた。
ところが、講演の数日前になって、役所の担当者(しかも女性!)から団体に「(望月の資料のうち)政治に関する部分はカットしてほしい」と申し出があったのだ。
(中略)
てやんでえ。政治とジェンダー問題を切り離せるわけがない。カチンときたので、要望は一切無視して100枚全部使った。「モ・リ・ヨ・シ・ロ・ウ・さん、がこんな女性蔑視発言をしましてね!」と、いつもより大きな声でそれぞれの名前と、やらかした内容を強調しておいた。会場は盛り上がったが、担当者は姿も見せなかった。

 レビュー
レビュー


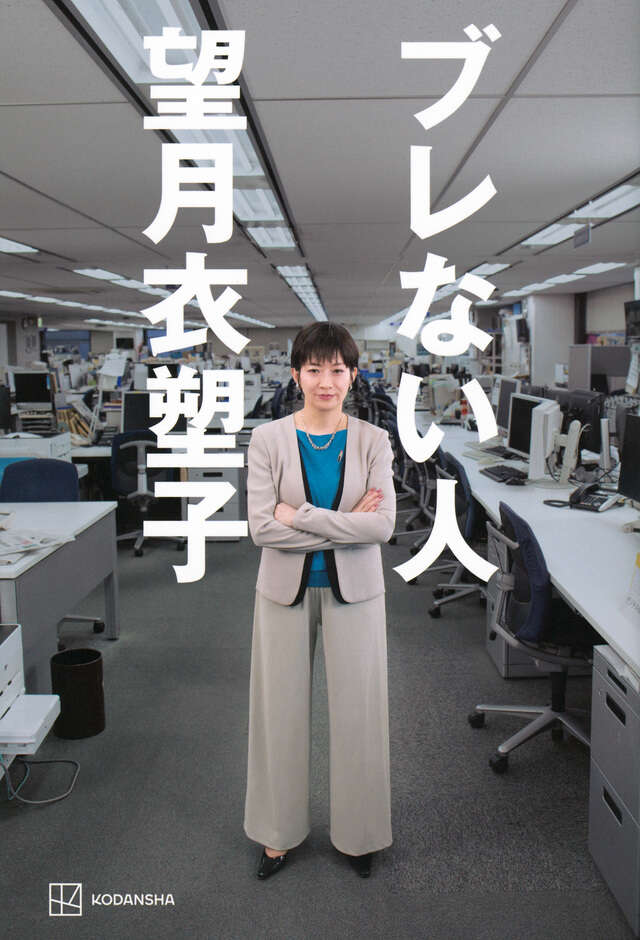










 特集
特集