本書は、大正・昭和・平成の時代に筆を執った五人の「危ういもの書きたち」の作品を論じながら、現代というこの「昏(くら)い時代」の陥った危機的な姿を透かし見るとともに、そのどん詰まりのさまをあらためて噛み締めようとしたものである。文学作品をよりどころとしてのいささか主観的色合いの濃い現代批判のつもりである。
いずれも、「本物」の大作家なるもの――そんなものはそもそも存在しないのだが――からいささか逸脱したもの書きたちだ。世の現実を拒否しつつも、それに代わるポジティヴな見通しを打ち出せないまま、ないしは打ち出して暗礁に乗り上げたまま、挫折していったもの書きたちである。本書は、彼らが、押せどもびくともしない現実にはね返されてもがきながら、何を思い、何を希(ねが)い、何を試みようとしたのかを、あくまで具体的な作品のうちに辿った。彼らの希いと挫折は、抽象的な思想の言葉ではなく、具象を命とする創作という血の通った肉体的な語りにおいて、われわれの共感と深読みを引き起こし、現代のどん詰まりの姿を見せてくれているように思えるのだ。
有無を言わさぬ経済と集団幻想が世界を覆い尽くし、人も物も事もすべてが、リアルでありながらリアリティの欠落した記号として操作の対象となり、数値に変えられ売り買いされてゆく。世界が自閉的に膨れ上がり、出口が塞がれて、外の世界がどんどん見えなくなってゆく。人々は、計算され尽くした自動人形となって、あらぬところへ拉し去られてゆく。たんなるオン・オフ信号と化した人間、そんな人間に、未来への新たな力が生まれてくるはずもなかろう。人は背中を曲げ俯(うつむ)いて歩くしかない。いささか誇張した言い方だが、これが、明治以来がむしゃらに突き進んできた資本主義化と近代化の行き着いた姿なのだ。人間の文化・文明が、進歩進歩の喧しい合唱の中で、何やらおぞましい終末の瀑布(ばくふ)に向かってとめどなく押し流されていく、そんな気がしてならない。
最初に登場するのが、大正時代に活動した宮嶋資夫(1886~1951)。おそらくそこまで知名度は高くない人だが、知らなければ知らないほど衝撃は大きい。手加減抜きの暴力、どん詰まりの貧窮、社会の底辺に生きる者の怨嗟に溢れたパワフルな作家性は、万人受けとは言えなくとも、こんな作家が100年以上前の日本にいたのかという驚きは間違いなく与えてくれる。
彼のデビュー小説『坑夫』(1916年発表)は、鉱山で働く主人公・金次が、周りの同僚たちに嫌悪と怒りをまき散らした挙げ句、集団リンチで悲惨な死を遂げる姿を描いた衝撃作。実際に職を転々とし、過酷な労働環境に身をやつし続けた宮嶋自身の人生遍歴が大いに反映されているという。
宮嶋は、金次の憎悪と苛立ちと暴力を描くことを通して、近代の人間の歪んだありように、侮蔑と絶望の目を向けているのだ。小説「坑夫」は、そうした意味で、「大正労働文学」だとか「揺籃期プロレタリア文学」とかで括るよりも、たとえば「近代底辺文学」とでも枠づけし、「カインの末裔」などと合わせてそこに組み込むのが、まだしもふさわしいかもしれない。
だが、なぜなのか。なぜ大正時代の初めにこうした憎しみと暴力の文学が「労働文学」とは異なるアナーキーな形で噴出したのだろうか。
続いて登場するのが、挫折の大家・太宰治(1909~1948)。一般的には破滅型作家と評される太宰作品のなかに、著者が見るのは絶望の果てのユートピア=無何有(むかう)の世界。醜く救いのない現世のすべてから解放されたときに現出する幻が、太宰作品のキーワードであるという。
欲望に駆られて市民社会の息苦しい縛りからはみ出し、孤立した死へと追い詰められる。そしてその死の一歩手前で、自由な生の場としての無何有の幻を、まるで沈黙の祈りのように一瞬浮かび上がらせる。太宰の創作には、そうした三鼎(みつがなえ)の構造がさまざまにうかがえる。掟破りによるリアルな滅びの背後に、無何有の幻を髣髴とさせること、彼の文学の本領はそこにあると言ってもいい。無何有の世界とは、掟破りに向けられた死の暴力を押し戻そうとする生の最後のあがきでもある。
3人目は、太宰治の友人であり、『太宰治情死考』の著者でもある坂口安吾(1906~1955)。太宰以上に型破りな文学的冒険を繰り広げた坂口もまた、戦中戦後の悲惨な焼け跡、人の心も日常も荒廃しきった世界から、思いもよらず生じる美や希望を描出した。著者はこの領域を、イギリスの哲学者ジョン・ロックの言葉から「タブラ・ラサ」(拭われて文字の書かれていない白板。経験から得られる諸観念をもたない白紙状態)と名付ける。
安吾の文学は、そうした意味で、もとより大きな断念を前提とした文学、挫折を覚悟の上での文学でもあるということだ。断念と挫折を前提としているゆえにこそ、タブラ・ラサがタブラ・ラサとして存続していくのだ。到達を断念した挫折の文学――繰り返すが安吾自身、それは最初から予想しまた覚悟していたところであり、じっさい「犬の生活」のうちに常に内心忸怩たるものを抱えながら、その不安な心境を押し隠すようにしてもの書きの生活を続けていたに違いあるまい。
一応ことわっておくと、著者はこれらの作家たちの再発見は促しても、過剰な再評価までは強制しない。それでも読者は、その破天荒な内容と生きざまに興味を抱かざるを得ないだろう。
たとえば、靖国神社を参拝する2人の老男女を描いた短編『地下鉄の昭和』の解説文は、秀逸な幽霊譚のごとき不気味さを読者に伝える。著者曰く「誇張した独りよがりな勿体(もったい)や感傷が目につき、ヒロイックで深刻な叛逆者気取りが鼻につく」という桐山作品そのものより、その魅力を巧みに伝えているのだろう。
自分たちを翻弄し、捨てて顧みることのなかった天皇制のふところ深くに消えてゆく二人の老いた犠牲者。桐山は、彼らの悲惨にして愚かな姿を、あえて感情をまじえずに描くことによって、戦後の無責任な時代に形を変えて生き延びている天皇制と、それを背後で支えている日本の現実を、おぞましい不条理として読者に突きつけてくる。(中略)そこには、性懲りもなく自ら破滅に向かって歩んでゆく人間の異様さがむき出しになっている。天皇制は、人間に巣食っているそうした不気味さによって下から支えられてもいるのだ。人間とはなんと矛盾した忌まわしく度し難い存在なのかという絶望と同時に、天皇制に対する怒りと叛逆が、避けがたい思いとなってじわりと湧き上がってくる。
表題は「スターバト・マーテル」、筋立ても表現もすこぶる大袈裟な独りよがりと言うほかない物語である。「黝(くろ)い顔」の十二人の死者たちがゾンビのごとく墓穴から抜け出して革命行動を始める話で、もはやリアルさもへったくれもなく、暗く異様な雰囲気だけが物語を圧倒している。
「スターバト・マーテル(聖母は立てり)」とは、「悲しみの聖母」と邦訳されている古くからのカトリックの聖歌の一つで、死にゆくイエスを悲しみ嘆く聖母を歌ったものだが、桐山はここに、革命の志なかばで倒れた「山岳ベース事件」の死者たちを弔う意味をこめた。むろん、ただ弔うだけではない。死霊として甦った彼ら十二人をイエスの十二使徒に重ね、その行動に来るべき革命の幻想を見ようとしたのである。
世に天使と呼ばれる可憐な子供の姿に、ユートピアならぬディストピアが映り出ている。そして、子供の呼び寄せるそのディストピアの中で、愚かにもいずれ死滅してゆくだろう人間たち。野坂はいくつかの作品で、そんな滅びゆく人間たちを、可憐にして妖しい花がじっと見つめている妄想のうちに描いた。死んで遺棄された人間たちの生まれ変わりとでも言おうか、何も語らず人類の破局をみつめる花たちである。
彼が見つめているのは、こう言ってよければ、現代の終わりなき終焉(エンドレス・エンド)の姿である。終わりなき終焉に終わりをもたらそうとするのだ。自らも含めたうとましい現実を破壊し、混沌(カオス)の世界を作り出すことが、彼の唯一の――ある意味で絶望的ともいえる――願いなのかもしれない。

 レビュー
レビュー


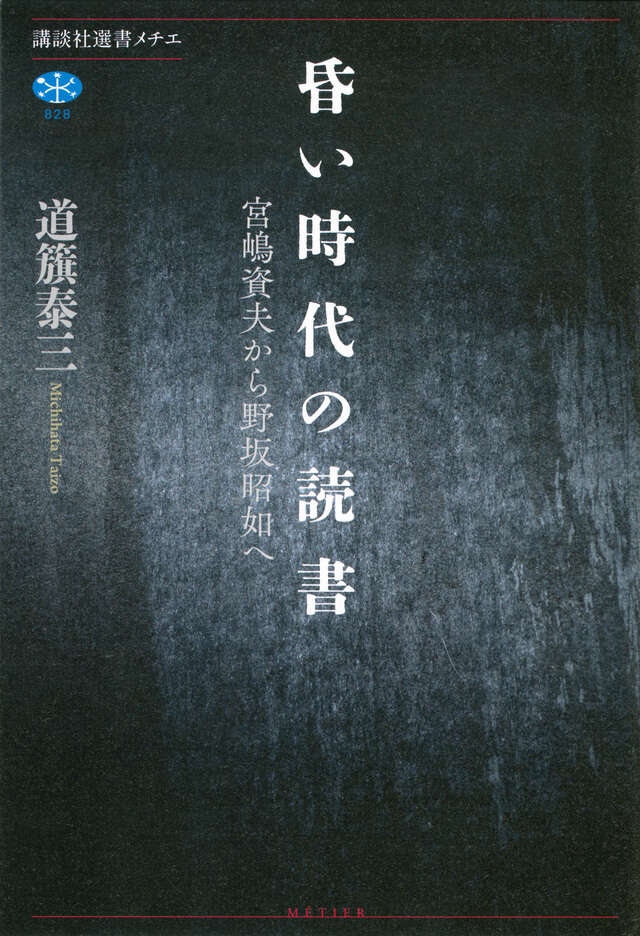









 特集
特集
