
密着ドキュメントでは描かれない警察の姿
『密着! 警察24時』みたいな番組を見て、「おまわりさん、大変やなぁ」とつぶやく。そんな漫然とした平和を享受しているあなた! 本書を読むと、ニュースで報道される事件が、今どういう捜査を行い、どういう局面にあるのか、理解度がめちゃくちゃ上がります! 最近の「上野飲食店経営者夫婦殺害事件」でいえば、「遺体発見後、捜査1課が防犯カメラで不審車の特定を行い、リレー捜査を行なっているタイミングで平山容疑者が出頭してきて……」くらいのことは推察できてしまいます。
著者は共同通信社などの記者として警察庁・警視庁・大阪府警をはじめ全国で重大事件を追ってきた甲斐竜一朗氏。グリコ・森永事件、地下鉄サリン事件、世田谷一家殺害事件、神戸連続児童殺傷事件からルフィ広域強盗事件まで、ありとあらゆる事件で「いかなる捜査が行われたか?」「なにが犯人逮捕の決め手となったか?」が記されている。本書が興味深いのは「刑事捜査の変遷」が分かるところ。技術革新、組織改革、技術の伝承など「これはトヨタの話ですか?」と思うほどの、たゆまぬ改善の連続。それを積み重ね、変革する“しなやかで強い” 警察組織の姿が浮かび上がる。
近年、刑事捜査で最も重要視されているのが防犯カメラによる初動捜査だという。例えば保釈中だったカルロス・ゴーン被告が密かに日本を出国したとき、逃亡経路の解明に投入された警視庁捜査1課の「初動捜査班」は、わずか4日で全行程を割り出している。この「初動捜査班」とは、
現場周辺の防犯カメラの映像から犯人とみられる人物を見つけ出し、そこから次々と防犯カメラの映像をたどりながら、犯人に迫る「リレー捜査」のスペシャリスト集団だ。
現場からどう逃げたかを追跡するのが「後足班」で、犯人がどう現場にやってきたかをさかのぼるのが「前足班」。その一方の捜査が行き詰まっても、もう一方の行動を分析すれば、どんな動きをするか読み解けるという。
警視庁の重要犯罪の検挙率は平成に入りほぼ50~60%台で推移していたが、2010年の63.4%を境に上昇し、18年は初めて90%を超え93.9%を記録した。このうち殺人、強盗、略取誘拐・人身売買は過去発生分なども含めて解決したため、この年に100%を突破している。
プライバシーの侵害や、監視社会についての懸念はあるとして、この検挙率100%超えの事実をどう受け止めるか? 電柱から自分を見つめるあのカメラについて、思わず考えてしまった。
難しい技術の継承
防犯カメラやDNA鑑定(今や「565京人に1人」の精度に達している)といった技術革新の一方で、警察が抱える悩みもある。それは容疑者とされる人物の心を開かせ、供述を得る取り調べ能力の維持と向上についてだ。冤罪事件への反省、時代の趨勢として透明性や公平性が求められるなかで、いかに「自白」を取っていくか? 犯人とのコミュニケーション力、心理的な駆け引きなど、取り調べ能力は一朝一夕に身につくものではない。本書の第3章「真相に迫る」では、名取調官と呼ばれる人たちのエピソードが紹介されているのだが、これがすこぶる面白い。
オウム真理教信者による拉致事件容疑者を取り調べた元捜査官が語る
「取り調べはハート・トゥ・ハート。情けをかける情ではなく、心の通じ合う情を交わさないと、本当のことは聞けない」
とか、死刑囚と対峙した捜査官の
「真剣にがーっとなるだけやったら容疑者は話さへん。そんな余裕のない取調官に自分の命は渡されへんやん」
と、「こういうベテラン、刑事ドラマによく出てくるよね」というエピソードばかり。長年にわたって磨き上げた取り調べ能力を、いかに次世代に伝承するか? この問題に対応するため、警察庁は警察大学校に「取調べ技術総合研究・研修センター」を設置。心理学の知識を取り入れるなどして、取り調べ能力の維持・向上に躍起だ。
本書のエピローグでは、まだ記憶に新しい「ルフィ広域強盗事件」が、いかに解決されたか記されている。この事件、人々の間では狛江市での強盗殺人事件、もしくは「ルフィ」というキーワードが広まって認知され、比較的短期間で逮捕に至ったというイメージがあるが、警視庁捜査2課が特殊詐欺事件で端緒を掴んだのは2018年のこと。渡辺被告らの犯罪グループへの捜査は、5年もの歳月がかけられていた。その執念もすごいが、通称「匿流」と呼ばれる匿名・流動型犯罪グループの摘発はそれほどに難しい。刑事捜査が進化するのと同時に、犯罪も同時に進化する。止まることのないその進化を知っておくことは、興味を満たす以上に、今の社会を正しく理解する助けになる気がする。
レビュアー

関西出身、映画・漫画・小説から投資・不動産・テック系まで、なんでも対応するライター兼、編集者。座右の銘は「終わらない仕事はない」。

 レビュー
レビュー






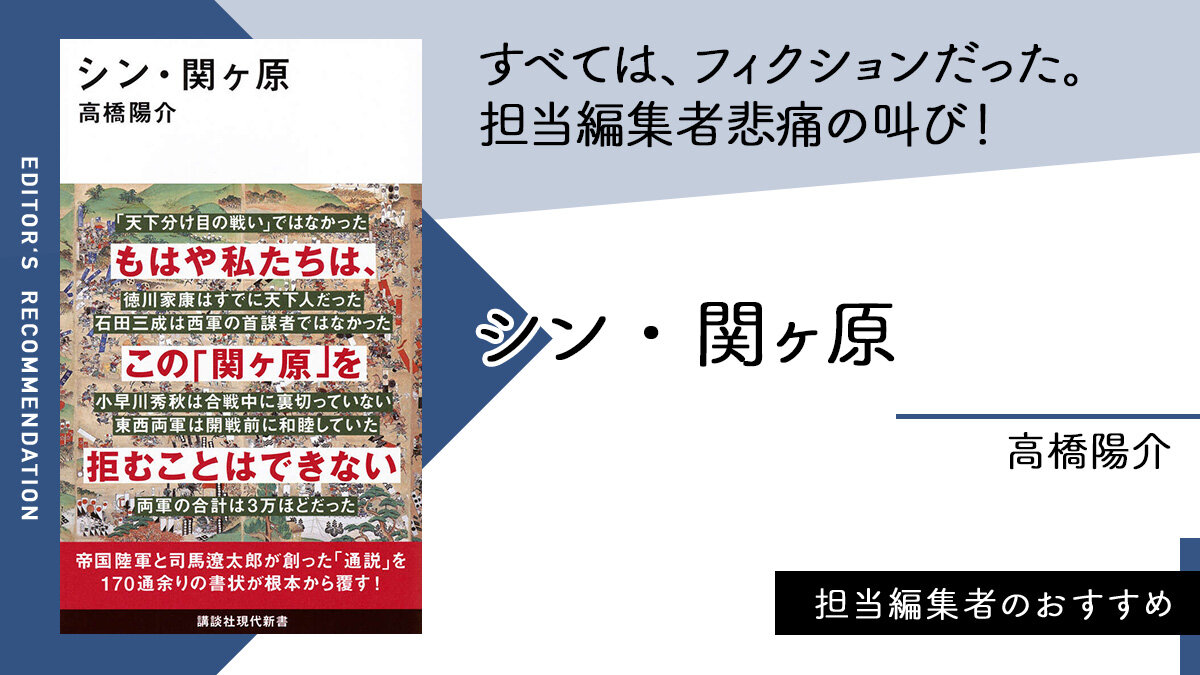
 編集者のおすすめ
編集者のおすすめ
 特集
特集
