
数的思考力を育てる
「40-16÷4÷2」の解はなんでしょう?
答えは「3」? 「12」? それとも「38」?
この問題、ごく簡単な計算に見えて、実は大学生の10人に1人が間違えるといいます。
こうした簡単そうな問題が解けず「算数は苦手」と思ったり、「確率」「期待値」などを「どうやって解いたか思い出せない、難しい」と敬遠している人も多いのではないでしょうか。
「昔は算数や数学の問題が解けたけど、今は解けない」「数学は学生の頃から苦手」という人の多くは、数の学問の基本である算数を「理解」ではなく「暗記」することで切り抜けてきたのかもしれません。
『昔は解けたのに…… 大人のための算数力講義』の著者である芳沢光雄さんはこういいます。
逆に理解を大切にした算数の学びを心掛けると、難しい数学の力を借りることもなく、工夫すれば解決できる問題はいろいろある。
「ある濃度の食塩水を作るのに必要な水と塩の量を求める」「店の営業時間とアルバイトの出勤日数から、店に必要なアルバイトの総人数を求める」など、日常生活で数的思考を要求される場面は意外に多いもの。なのに、昔学んだはずの記憶が蘇ってこないのは「数学が苦手」だからではなく、かつての暗記に頼った勉強法のせいかもしれません。
統計・確率・期待値・平均値……ビジネスシーンでもちょくちょく求められるこれらの思考は、すべて「算数」が根本にあります。大人の数的思考に必要なのは「暗記力」ではなく、数や算数への理解力、思考力です。
本書は、数学の源流にある「算数」の基礎を、大人が学び直すための一冊。数的思考を磨き、数字が読める大人になるための算数力講義です。
暗記の学びに頼らない
暗記の学びに頼らず、数的思考・理解力を身につけることがテーマの本書。
「数と計算」「量および比と割合」といったテーマごとに算数の問題を解説し、各節の最後には復習問題と解答・解説が続きます。
「数と計算」について解説する第1章は、紀元前における「数」の成り立ち、油や穀物を数える「トークン」の話題から始まります。「数とはなにか?」という問いには「整数・分数・無理数・複素数の総称」といった答えが返ってくることが大半ですが、本書では誰もがイメージできる言葉と文章で「数とは」を定義しています。
そこで「男の子と女の子が何人かいるとき、男の子と女の子には人数差があるのか、または同人数なのか」を確認する、こんな方法が挙げられます。
それは、男の子と女の子に一人ずつ手を繋いでもらうことである。すなわち、1対1の対応を考えるのである。
私は問題文を読んだとき「これを導き出す公式はあったかな?」と考えました。シンプルに考えれば一瞬でわかることなのに、算数・数学は「難しいもの」「公式を覚えていないと手も足も出ないもの」と思い込み、自分の頭で考えようとしていなかったことに気づきました。
ここで、冒頭の「40-16÷4÷2」の答えをみてみましょう。
40-16÷4÷2=40-4÷2=40-2=38
四則混合計算には以下のような規則があり、これを十分に理解していないと40-16の解を2で割ってみたり、40-16を4で割り、さらにその解を2で割るなどして「12」や「3」といった不正解を導き出してしまいます。
・計算は原則として式の左から行う。
・カッコのある式の計算では、カッコの中をひとまとめに見て先に計算する。
・×(掛け算)や÷(割り算)は+(足し算)や-(引き算)より結びつきが強いとみなし、先に計算する。
「暗記に頼らない」とはいえこのように最低限覚えておかなくてはいけない規則は図や記号などを用いて、「目で見て理解」できるようになっています。
また、この本は「読む速さ」と理解のスピードがほぼ同じになるように書かれていると感じます。これが読みやすさ・わかりやすさの大きなポイントです。先に挙げた「数」の定義も、整数・分数はさておき「無理数とは? 複素数とは?」といった用語でつまづくと、そこで思考が止まってしまいませんか?
たとえばこちらは「原価・定価・売値」について考える例題です。

「原価は~」「定価は~」と、用語の定義をはじめに書き、それらがどんな関係にあるかを図で示してあります。
ある商品の原価に2割の利益を見込んで定価をつけたが、売れなかったので定価の1割引の値段で売った。
のように、イメージしやすい「よくあるケース」をもとに、利益率を求めます。
原価を記号に置き換えることで、例題に設定された数値が式のどこに入っているのかわかりやすくなり、思考の要点が見えやすくなります。図や数式を自分の手でノートに整理しながら読まなくても、すっと理解できるシンプルさです。
「読めばわかる」というのは、メモやノートがなくても、この一冊があればスキマ時間に数への理解が深められるということ。社会人にとってうれしいポイントです。
生活の中にあるケースを通じて数的思考の方法を教えてくれる本書。なじみのない数学用語を知識として詰め込んだり、暗記した公式の中から解法を探らなくても「解ける」という自信をくれます。数や算数への苦手意識を拭い去ってくれるだけでなく、自分の頭で考える楽しさも教えてくれる一冊です。
レビュアー
ガジェットと犬と編み物が好きなライター。読書は旅だと思ってます。
X(旧twitter):@752019

 レビュー
レビュー






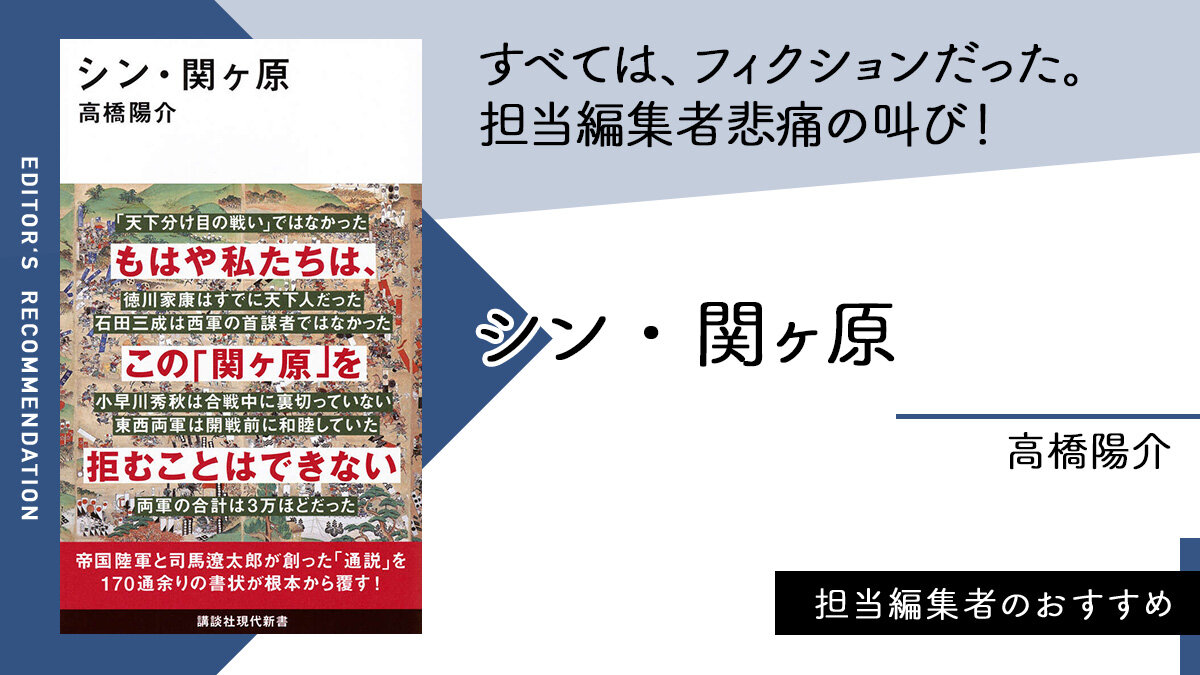

 特集
特集
