横浜中華街で発見された、ひとりの男の遺体。その殺人事件は、30年前に起こった3人の若者とひとりの警察官の失踪につながっていました。
あのころはまだ昭和の1981年。作中で描かれる当時の風俗は、恐らくは1965年生まれの著者、本城雅人氏ご自身の経験も密接に織り込まれていることでしょう。学生運動の余韻はすでに遠く薄くなりつつありましたが、バブルの狂騒はもう少し先。校内暴力の風が全国に吹き荒れ、そうした空気に浸る若者も多かった。
少しだけ後に生まれた私にも当時の空気はわかります。当時、都市伝説的に流布されていた話なのですが、ある高校生が朝鮮高校にケンカを売りに行ったところ、逆に近くでからまれた。当時、朝鮮高校の学生というと、「ツッパリ」の少年にとって宿命のライバルでもありましたが、その荒っぽいケンカで畏怖される存在でもありました。彼はその「威」を借りようとして「俺は朝鮮高校やぞ」とはったりをかましたといいます。しかし相手は笑って「俺もそこの生徒やけど、おまえの名前はなんていうねん?」と訊いてくる。しかし急には名前は出てきません。
ノ・テウとかキム・デジュンとか著名な人の名前でも言えばよさそうなものですが、それは後知恵というものであって、急場はなかなかそうもいかないものです。窮した彼は、とっさに目に入った札を見て「俺の名は営 業中や」と答えたと伝えられます(伝説には「ジュン ビチュウや」と答えたというバリアントもあります)。
懐かしい1980年代。私も、青のジャケットに黒のスラックス、ドレスシャツにカマーバンドという、ノームコアの現代から見たら卒倒しそうな服装でディスコパーティに出かけたことがありました。いっしょに行った友人は3800円で買った純白のタキシードを着ていて、それ系の職業と勘違いされて、からまれていましたが、思い出深い時代です。
しかし時代の風俗は共有できても、作中で描かれる3人の若者たちの青春は、私の物語ではありません。彼らの地元は横浜中華街。そして彼ら自身もまた中国籍。同じ日本で同じ時代を過ごしていても、地理的にも、アイデンティティとしても、私から見ると壁の向こうの物語です。
当時の中国系の人たちの社会は「日本の中における異邦人」というだけではなく、コミュニティの中でも台湾系の籍、大陸系の籍とふたつの勢力に別れ、血族の中でも分断が起こってしまうという複雑な状況だったそうです。この小説に登場する3人の若者、周志龍、陳亮、楊将一たちは大陸系でした。将一は日本人を母に持ち、日本の私立高校に通っていましたが、あるケンカをきっかけに中華学校に転校してきます。
同じ日本という物理空間、同じ時代に生きていても私と彼らの物語は違う。私は、彼らのようには自分自身のアイデンティティを強く意識する必要はありませんでした。時代はまだ’80年代。「自分も平凡なサラリーマンになるのかなあ」などという漠然とした生き方がまだ機能していた時代です。
一方、彼らの場合は、高度な技術を要する獅子舞の練習に打ち込み、将来に希望を抱くというという若者らしい面もありますが、自分自身のアイデンティティをいつも強烈に意識せざるを得なかった。
彼らのことを、不穏分子を生みだす潜在リスクとして監視の対象にする警察、中でも外事警察の存在は、彼らが社会の中で異質なコミュニティであるという現実を否応なしに突き付けます。彼らはいつも緊張とともにあった。俗な言い方をすると「ナメられてたまるか」という気持ちがいつもあった。そうした緊張とともに生きることは厳しいことでもあります。もし人が「ナメられてたまるか」という看板を下ろそうと思った時、それが「社会の中に埋もれよう」と思う時なのかもしれません。
ただ、彼ら3人の青春は厳しいことだけではなく、心から信頼できる仲間と過ごす幸福な時間でもあり、恋の季節でもあったのですが、しかしそれはある日、唐突に終わります。現代の刑事、山下渉は、所轄のベテラン、樋口とコンビを組み、彼らの失踪の謎を追っていく。その捜査の中で、数々の謎めいた武勇伝を持ち、今でも緊張の中を平然と生きているように見える「山手の蒋介石」と呼ばれる男に行き当たります。
著者の本城氏は、なぜこのような「社会の中の異質」を描いたのでしょうか。ただ「異質」を描いただけはなく、この作品では「異質からの視点」がありありと描かれています。まだ著者のファンとなって日が浅い私が想像をたくましくすれば、本城氏はいつも「普遍」ということを考えておられるのではないか。日本には、日本の「固有」の風土がある。独特の湿度があります。その情緒に則って物語を描くのもありでしょうし、それもとても難しいことです。しかし本城氏は固有より普遍的な感覚を追われるのではないか。
さらに、さらにこれはもう妄想の域ですが、それは本城氏が「野球」を描いた小説でデビューされたことにつながるのではないかという気もします。私もまた子どものころプロ野球選手の活躍に憧れましたが、しかしいつも「世界」を意識せざるをえませんでした。それはなにもややこしい話ではなく、たとえば王さんが偉大なホームラン王だとして、果たして大リーグでも活躍するのか。当時、子供向けの雑誌でも、彼我の球場の広さの違いなどにもちゃんと注釈がついていました。後に日本人選手がメジャーに渡る時代が来ましたが、このことは逆に「メジャーとNPB」という市場の違いを際立たせたようにも思います。
小説では、自分が何者であろうとするのかを強烈に意識し、それをやり遂げてしまった男。豊かな可能性を持っていたのに、人生を奪われ惨めな生を生きてしまった男。何者かであり続けるしかない男が描かれます。奪った男たち。奪われた男たち。その生が明らかになる時、読み手は固有の風土を越えて普遍的な「物語の魅力」に心をつかまれることになるでしょう。
現代ではもはや「何者か」であることが希薄な時代になってしまいました。かつては人はみな、技術を身につけた職人であったり、その道のプロである商売人であったり、安定した勤め人であったりした。しかし現代では、もはや曖昧です。こうした時代に、たとえそれが仮面をかぶったものであっても、強烈に「何者か」であろうとする人物像を突き付けられると、粛然とします。舞台は日本固有の風俗なのに、まるで海外作品のような叙述が同居する読み味は、他に類のない本城作品ならではの読書体験。お勧めです。
レビュアー
作家。1969年、大阪府生まれ。主な著書に〝中年の青春小説〟『オッサンフォー』、 現代と対峙するクリエーターに取材した『「メジャー」を生み出す マーケティングを超えるクリエーター』などがある。また『ガンダムUC(ユニコーン)証 言集』では編著も手がける。「作家が自分たちで作る電子書籍」『AiR』の編集人。近刊は前ヴァージョンから大幅に改訂した『僕とツンデレとハイデガー ヴェルシオン・アドレサンス』。ただ今、講談社文庫より絶賛発売中。
 レビュー
レビュー


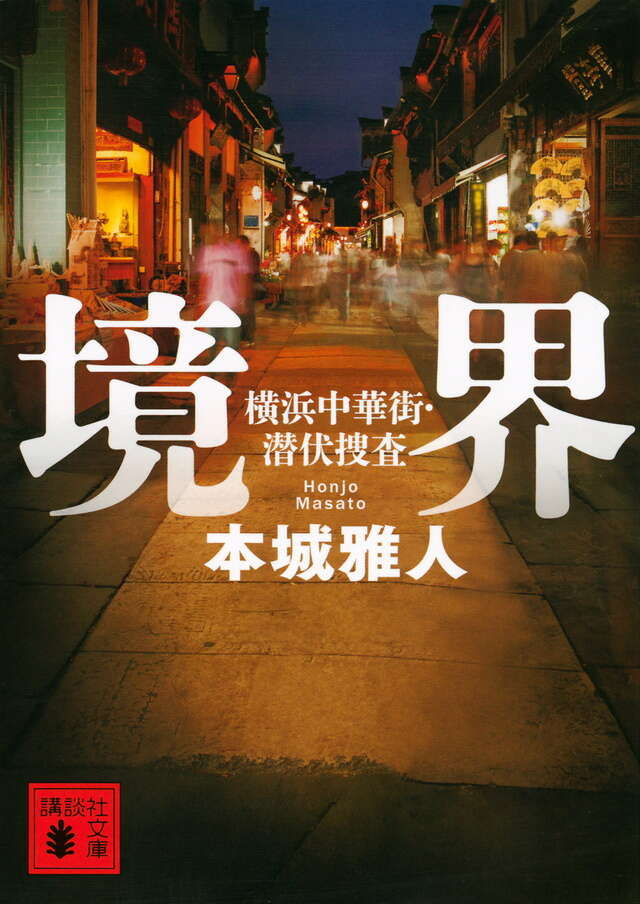




 特集
特集

