この30年をふり返るとき、私が大きな「曲がり角」と感じた節目は3度あった。第1に小沢一郎による政治改革、第2に小泉純一郎による構造改革、そして決定的な転機として第3に挙げるべきは、安倍晋三による長期政権である。
小沢の改革でうごめき始めた「右派ポピュリズム」の潮流は、小泉政治を経て、安倍政権下において遂に支配体制の一翼を担う勢力として正当化されるに至った。ネット空間での影響力を強め、リベラル勢力や政治的中間層を威嚇する存在となったこの潮流は、同時に巨額の財政赤字に目をつむり、政治の言葉を歪め、ついには政治資金をめぐる腐敗の温床となり、自民党の信頼を着実に蝕(むしば)んでいった。
にもかかわらず、この「右派ポピュリズム」は、安倍政権の「一強体制」を支えた柱だった。安倍が凶弾に斃(たお)れた後も、その影響力はなお強く、菅、岸田政権を陰に陽に支配した。そして今や、石破茂をはじめとする旧来の保守勢力を離れ、参政党のような新興勢力に憑依(ひょうい)しようとしている。
「保守本流」とはなにか、改めて問う1冊
この結果を受けて、ネット上の保守を自認する面々(多くは“ネトウヨ”とも言われる人たち)は、近年稀(まれ)にみる盛り上がりを見せている。彼らに言わせれば故・安倍元総理の遺志を継ぐと明言している彼女こそが「真の保守」であり、自民党内でも長く安倍ら清和会と敵対する存在であった石破前総理は「媚中左翼」に見えるらしい。
また、逆にネット上のリベラルを自認する人たち(明確な左翼系も含む)が、一様に石破前総理にかなり好意的なのも不思議だった。
私の認識では、石破氏は「歴史認識はかなり真っ当なので道は踏み外さないだろうが、安倍元総理をはるかに超えた対米強硬派の右翼」であり、今や希少となった「対話できる昔ながらの保守」なのだが、ネット上の評価は大きく異なるようだ。「保守」という言葉の意味が、この数年~数十年で変質しているように思う。
本書『自壊する保守』には、私が感じていた「保守という言葉の変質」がなぜ、どのようにして起きたのか、その長年にわたる流れが平易な言葉で語られている。著者の菊池正史氏は1968年生まれ。日本テレビ政治部に所属し、現在も第一線で活躍する政治ジャーナリストである。
本書では、まず「保守本流」の定義を「吉田茂から始まり、田中角栄で完成した政治」と位置付ける。その根底にあるのは「経済優先」かつ「反戦」であり「軍事力に依存しない平和主義」。そして社会を分断させないための「根回し文化」だという。
一方で、鳩山一郎から岸信介(安倍晋三元総理の祖父)、さらには小沢一郎、小泉純一郎から第2次安倍政権へと繋がる流れを「保守傍流」と表現。彼らは「保守本流」の政治哲学自体を「戦後レジーム」と断じ、そこからの脱却を目指していく。
キーワードとなるのは「強いリーダー」「新自由主義」であり「行動と実績の右派ポピュリズム」。「保守本流」が根回し文化を駆使して「2~3割の支持層に加えてさらに2~3割の『グレーゾーン』『中間地帯』を味方につけること」を目指し、「できるだけ多くの人間が“なんとなく許容できる落としどころ”」を探し続けていたのに対し、彼らは「絶対的多数決主義」を採用。「一人でも、一票でも少なければそれは敗者」と断じる。
本書は「保守本流」の政治がかつての日本で広く受け入れられていた理由(社会風土や政治環境)に加え、逆に今、かつての「保守傍流」がむしろ保守を自認する人たちの主流派に近い地位を得るようになった流れも、詳細に解説。日本の戦後「保守政治史」の大枠の流れがわかる1冊と言える。
自壊の道を歩む「保守本流」が「右派ポピュリズム」にトドメを刺されるまで
小泉の「保守」は、吉田や田中の系譜に連なる「保守本流」とは、根本的に異質なものだった。小泉も「二度と戦争を起こしてはいけない」と繰り返していた。しかし、小泉の政治から、戦争の影を引きずった「保守本流」の本質は欠落していた。その本質とは、権力を抑制的に行使することであり、人々の苦しみや悲しみに手を差し伸べようとすることだ。そして敵とも妥協し、広大な中間地帯を作ることである。
「抵抗勢力」という敵と闘う刺激的な劇場で、強権を振り回す小泉の政治からは、本当の戦争を知る世代が語り継いできた教訓を見出すことができない。「保守本流」とは似ても似つかぬ、「異形の保守」の源流なのだ。
もちろん「保守」や「革新」というイデオロギーの問題にとどまらず、なぜ第2次安倍政権が長期安定政権となり得たのか、その理由や社会背景についても解説。安倍政権の経済政策の根幹であった「アベノミクス」の本質とその評価、さらには一強だった安倍政権が崩壊に向かう原因となった、モリカケ問題や桜を見る会の話なども網羅している。
個人的には、安倍政権については森友問題から派生した「公文書改ざん」、および「たび重なる(118回にもおよぶ)虚偽答弁に代表される過度な国会軽視」、さらには「アベノミクスを粉飾する統計偽装をはじめとした虚偽の成果アピール」の3つがもっとも大きな問題だと思っているのだが、それらについても事実ベースでしっかり触れられていた。
一方で、安倍政権の意外な面として「弱者にも意外と優しかった(子育て、介護支援など社会保障の拡充)」など、一般のイメージとは少し異なる側面についても、しっかり評価されていたことも興味深い。アベノミクスのベースであったリフレ派の主張と、その政策の強引な実現が残した、まさに今直面している負の遺産についても解説されている。
その上で、極めて不安定な世界情勢を背景に、小泉政権で急速に伸び、安倍長期政権がじわじわと育ててきた「右派ポピュリズム」が「保守本流」を崩壊させてきた流れを紹介。
その前提として「保守本流」側が長年にわたり抜け出せなかった「保守本流の自壊に繋がる本質的な失敗」についても、厳しく評価している。
その言葉の裏からは、かつては「保守傍流」だった「右派ポピュリズム」が、今、日本の政治に歓迎すべからぬ分断を生んでいることへの強い懸念も、そこかしこに感じられた。
個人的にも「右派ポピュリズム的な“言葉の軽さ”が席巻している今の政治状況」ほど恐ろしいものはないと感じているので、著者のこの強い懸念も共有できる。
最後に遺された「保守本流」の大物政治家、野中広務が自身の引退の約10年後、国会に参考人として呼ばれたときに発した言葉が、本書の後半に記されている。安倍政権の強権的な政治的決断の進め方に対する警鐘が、強く心に残る。少しでも興味を持った方には、ぜひご一読いただきたい1冊だ。

 レビュー
レビュー


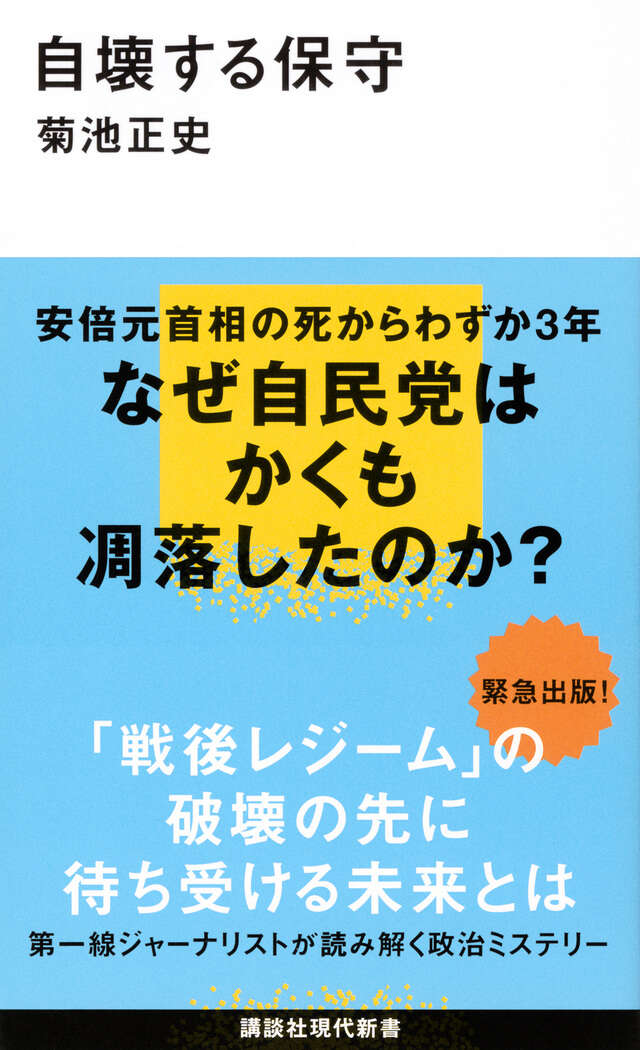










 特集
特集
