おバカキャラで笑いを届けてくれたつるの剛士さんが、今では5人の子どもを育てる“見守り育児”の実践者に。そんな彼が自身の子育てメソッドをまとめた著書『「心はかけても手はかけず」つるの家伝統・見守り育児 つるのの恩返し』には、家族への深い愛と、読者の心をそっと軽くするような言葉が詰まっています。
育休で深まった「子育てパパ」としての関わり
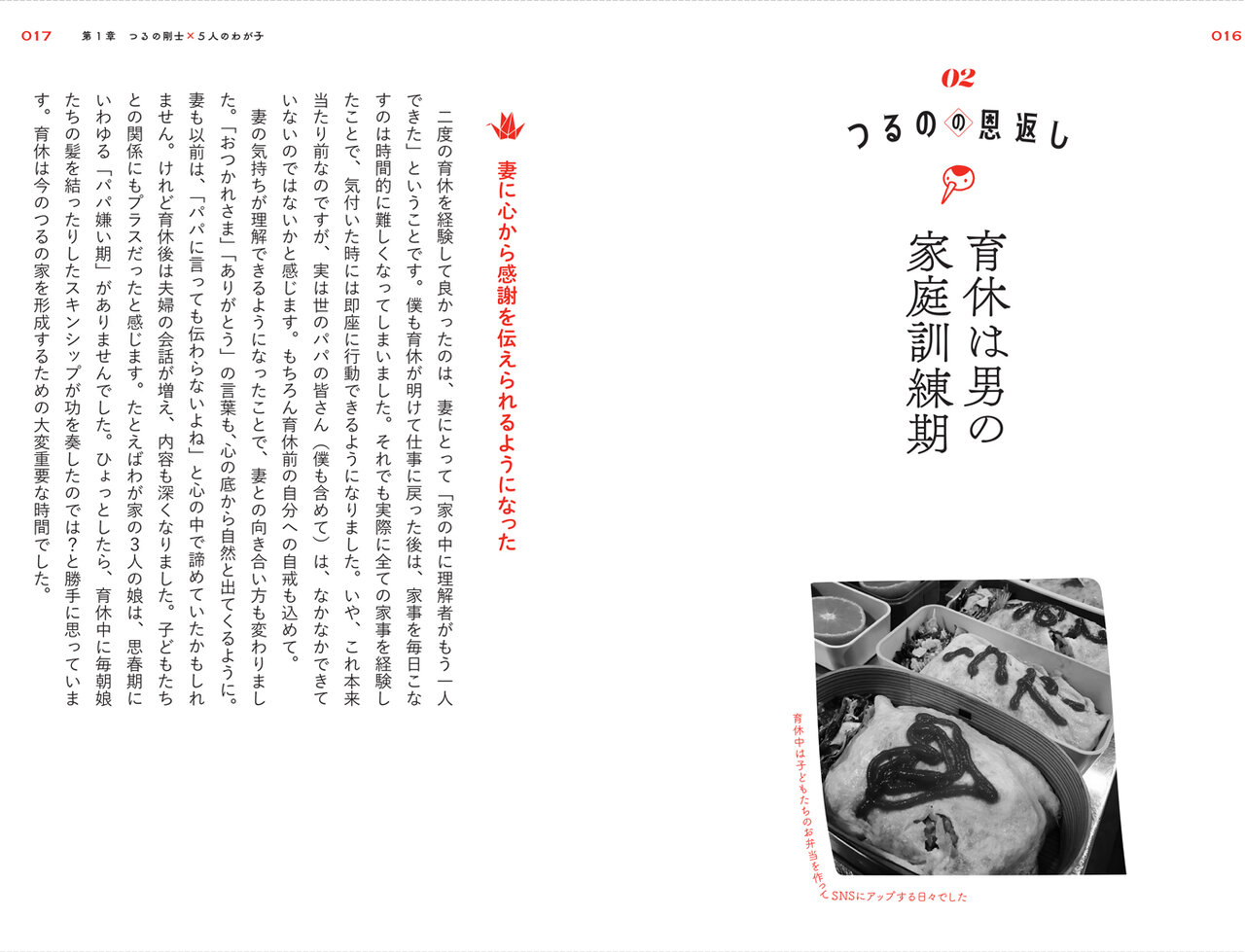
「手を出しすぎない。でも、ちゃんと見ている」
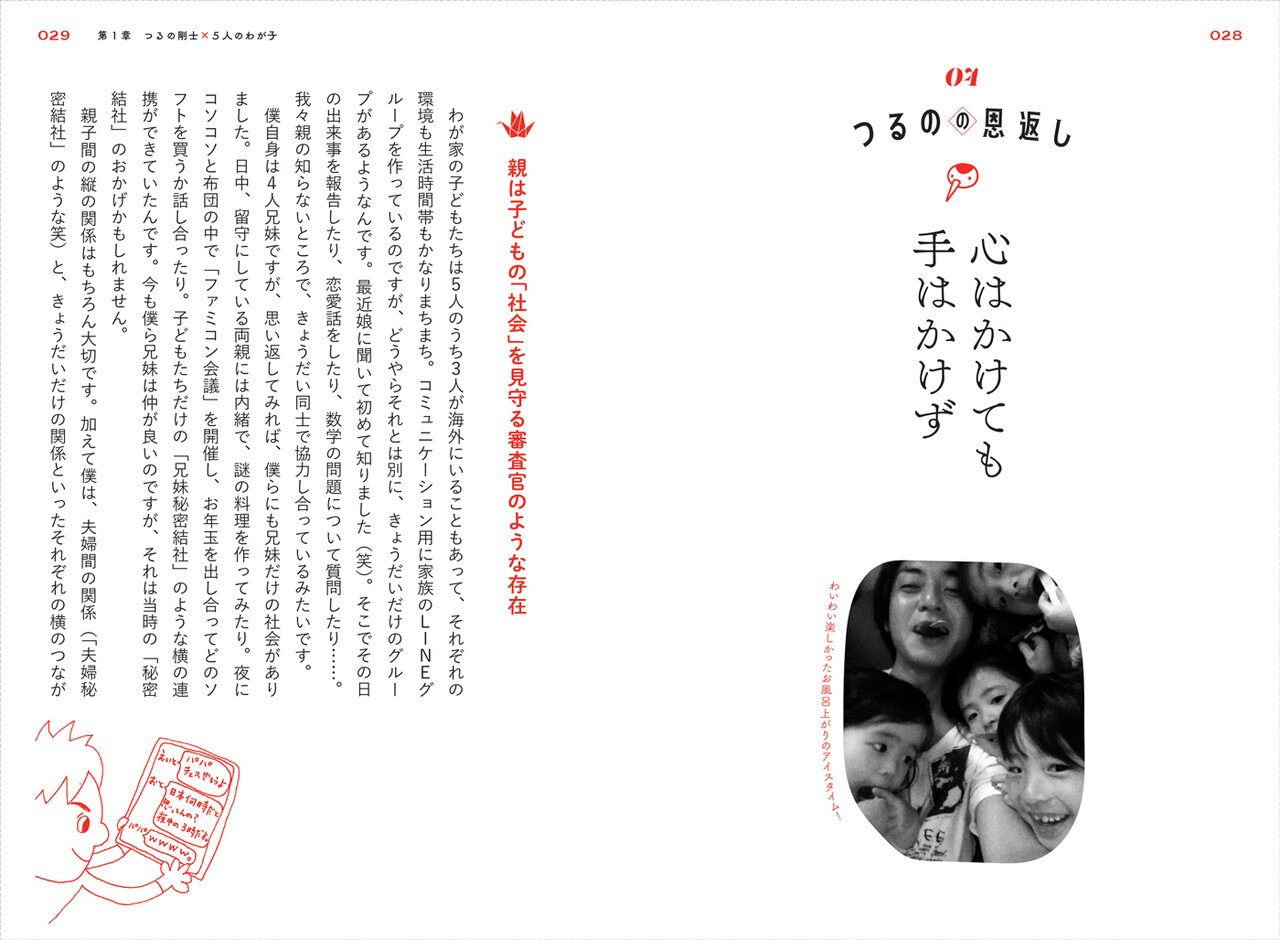
見守るって、こういうことかもしれない
そんな私の迷いに、本書はやさしく光を当ててくれました。
「手はかけずとも、目はかけ続ける」──。
子どもが何かに夢中になっている瞬間、目を輝かせている瞬間を、絶対に見逃さないようにする。その眼差しこそが、見守り育児の本質だと感じました。手を出すことは、実は“見なくても”できてしまう。でも、子どもの心が動いた瞬間をしっかり見つめて、それを応援するような関わり方を我が家でもやっていこう! そんな勇気をもらいました。
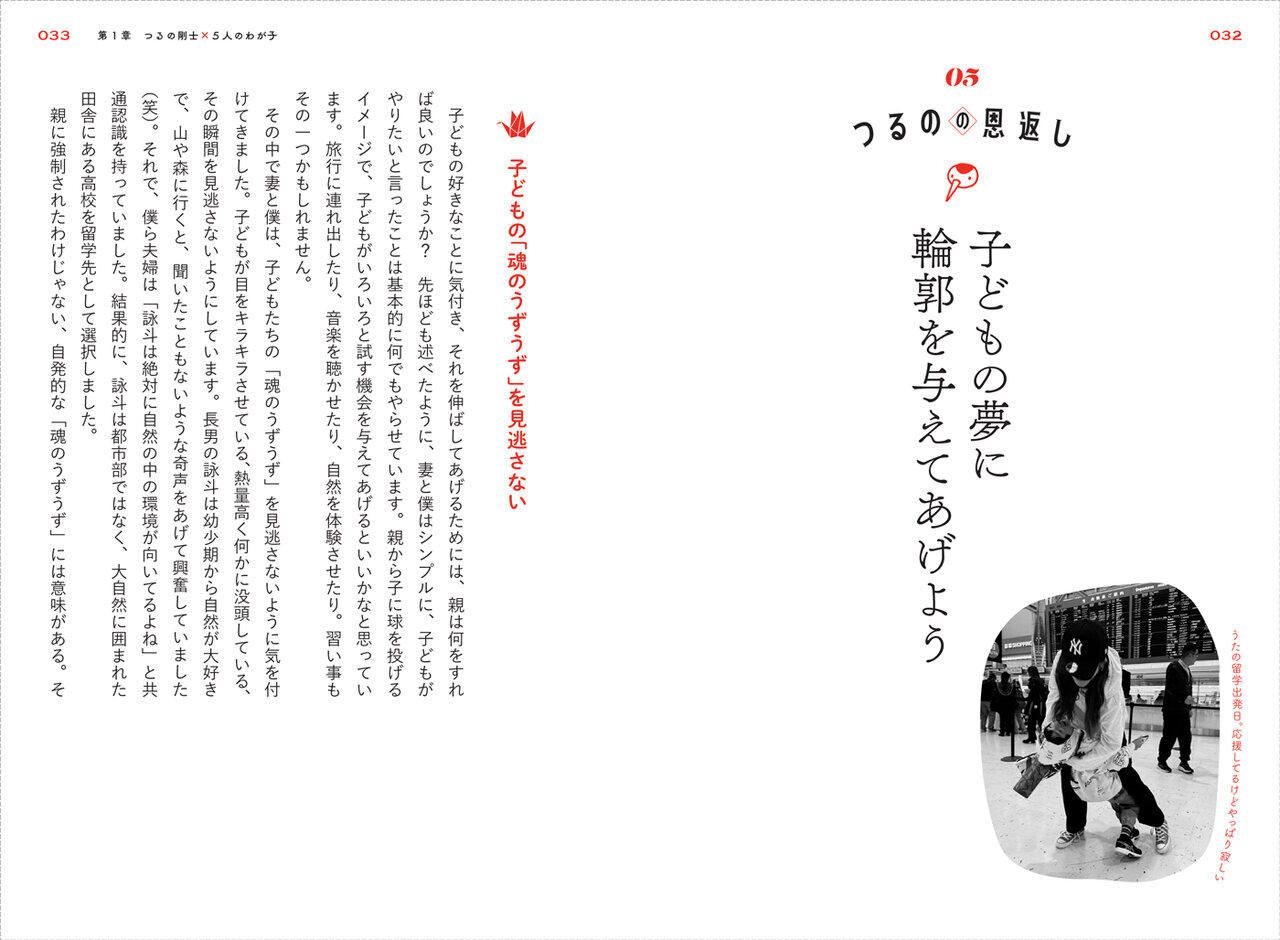
家族みんなで、ひとつのチーム
“家族の中心で太陽のように笑う父親”というイメージは、バラエティで見せる姿と地続き。どちらも嘘のない、まっすぐな彼そのものなんだと思います。
そして、育休をきっかけに育児へ深く関わるようになったつるのさん。その経験から築かれた夫婦関係や家族の形は、まさに「令和」の理想形だと感じました。
つるの家は、「夫婦は対等」と言い切るのでもなく、「親が子を導く上下関係」とも違う。家族全員が“チーム”のように、それぞれの得意を活かしながら協力し合って日々を過ごしているのです。ときには子どもと一緒に全力で遊び、ときには“ファイナルウェポン”として父の威厳を見せる。そんな柔軟さとあたたかさが、つるの流・見守り育児の魅力だと感じました。
夫婦で読みたい「令和の子育て」のヒント
焦らなくて大丈夫。つるのさんが、あの頃と変わらぬ笑顔と優しさで、そっと肩の力を抜く方法を教えてくれます。
子どもが心を動かしている瞬間、あなたはそばで気づけていますか?

 レビュー
レビュー












 特集
特集

