帚木蓬生氏の小説です。2004年に刊行され、その後2007年には文庫にもなっています。舞台はタイトルの通りアフリカ。主人公は日本人で、名前は作田新。遠くはなれた大地で、医療に従事する医師です。
作中、主人公は、かの国の人々に「なぜ日本人がこの国のために、尽力してくれるのか」と何度か言及されていますが、これはある意味で作者に向けられた言葉でもあるのだろうと思います。なぜ日本の作家が、アフリカの人を思いアフリカを舞台にした物語を描くのでしょうか。
実は帚木氏がアフリカを描いたのは二度目。本書は1997年に刊行された『アフリカの蹄』の続編的な物語になります。『蹄』での作田はまだ若く、心臓移植の技術を学ぶためにアフリカに留学していました。その地であるウイルスを用いた陰謀を知り、彼は命を懸けて黒人を差別する人々と戦うことになります。
本書はその12年後。アパルトヘイト政策は終焉し、ついに黒人による政権が成立しています。しかし黒人の苦難は終わらず、エイズ禍という恐ろしい災害に陥り、苦しみ抜いていました。作田はアフリカで家族を築き、この地に骨を埋めるつもりで暮らしています。
アフリカの医療の厳しい状況は、1万人以上の犠牲者を出した、2014年のエボラ出血熱の流行であらためて認識したものでした。作田のいる国では(作中、国の名は明言されませんが、読むとはっきりとわかります)10人にひとりがエイズに感染。しかも一日に200人もの子どもが、感染して生まれてくる。
先進国の援助はありますが、真に未来を見据えた施策とは、実は言えない。「知財の保護」という名目で製薬会社の論理が優先され、援助の手は人々に及ばずにいます。しかも、ようやく成立した黒人政権も、人々を助けるより自らの権力確保を優先させている。
いったいこの地獄はいつ果てるのか。厳しい状況ですが、しかし人々の暮らしの中に希望の光も見え始めています。面白いことに、作中で描かれるその光の担い手はしばしば女性でした。
しかしその一方で、苦しむ人々をさらに蹂躙する密かな“実験”が行われていました。現地医療を通してその陰謀を知った作田は家族とともに立ち上がります。
20世紀の終わり、これからの歴史はもっと穏やかなものになるという予想もありました。超大国による全面戦争の危機は去った。大きな争いは終焉したと。
しかし21世紀に入り、現実の世界は厳しさを増しつつあります。アメリカでは人々が分裂しつつある。中東ではアラブの春以降、混乱が収まらず、中世的な統治の空白地帯までもが出現。武装組織が侵食しています。ヨーロッパでは難民が流入し、大規模なテロが起こった。世界史はすでに激動の時代に足を踏み入れたと見るべきなのでしょう。
極東の島国にいると、こうした世界の過酷さは、物理的には遠い話になってしまう。しかしいつまで「遠い話」でいられるのでしょうか。こうした世の理不尽に対して、自分はどのように向き合うのか。実感するのか。
帚木氏はご自身が医師でもあり、安楽死、臓器移植など人の生の根幹に関わるテーマに挑まれる作家です。そうした帚木氏は恐らく、遠いアフリカの現実を知って、そこに生々しい怒りを抱かれたのでしょう。悲しいではすまない。遠い話でもすまない。いつか自分たちの危機にもなる、という実利だけでもない。人としての怒り。
今の時代、ネットを通して遠い国の情報も、おびただしく入ってきます。そうした遠い国の話に接して、自分はなにを思うのか。怒ることにも意味はある。思うことにも意味はある。
遠い国の現実を、我が痛みのように感じて紡ぎ上げた帚木氏の小説を読むと、ひとつの指針が見えたように感じます。今の時代にこそ、読みたい物語です。
レビュアー
作家。1969年、大阪府生まれ。主な著書に〝中年の青春小説〟『オッサンフォー』、現代と対峙するクリエーターに取材した『「メジャー」を生み出す マーケティングを超えるクリエーター』などがある。また『ガンダムUC(ユニコーン)証言集』では編著も手がける。「作家が自分たちで作る電子書籍」『AiR』の編集人。近刊は前ヴァージョンから大幅に改訂した『僕とツンデレとハイデガー ヴェルシオン・アドレサンス』。ただ今、講談社文庫より絶賛発売中。
近況:ガンダムの話をしながら、美味しいローストホースを食べるという会に参加することになりました。
 レビュー
レビュー


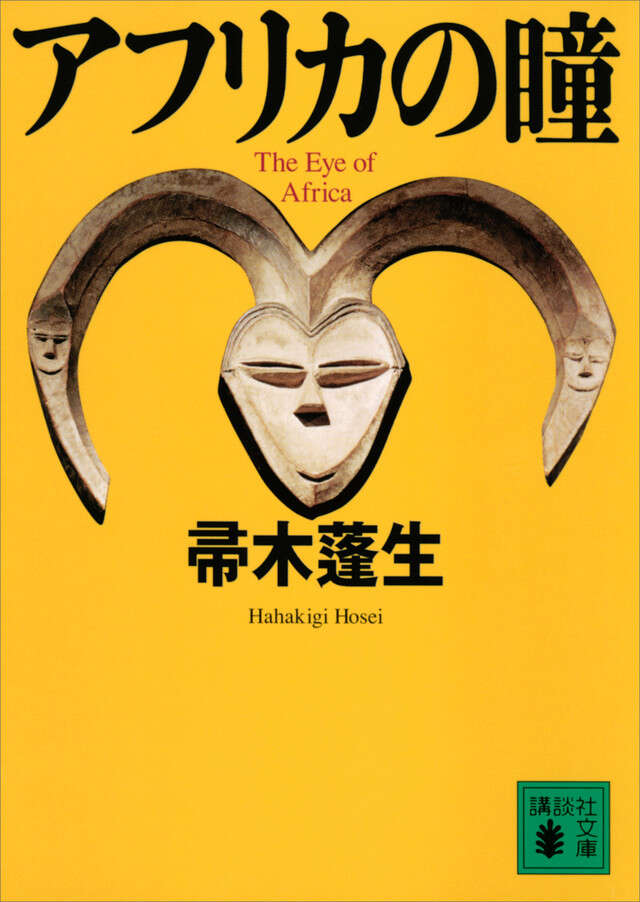





 特集
特集
