神道というものは思ったよりやっかいなものかもしれません。私たちの習俗には神道の影響、あるいは起源が神道に結びついているものが数多くあります。各地の神社などのお祭り、初詣等の行事も多かれ少なかれ神道と関係しています。もちろん、そのような行事に参加しているからといって神道信者というわけではありません。とはいっても初詣の神社で署名活動をしているグループは神道信者(神道グループの関係者)だとは思うのですが。
“日本は神の国”といった元首相がいましたが、この場合の神は戦前の“国家神道”につながりかねないものです。戦争を引き起こすイデオロギーとなった“国家神道”は復活させてはならないと思いますが、タブー視するだけでは何の解決にもなりません。神道を正確につかむ必要があります、間違った歴史を繰り返さないためにも。それにはこの本がうってつけです。
“神道”がどのように“神”を考えていたのか、それはどのような変遷を遂げていったのかを知ることは、少なくとも“神がかり”に惑わされないことにはなると思います。この本は日本人は“神”をどうとらえていたのか、そしてその上にたって、神道思想というものがどのように構想され、変遷してきたかを一望のもとにしたものです。
元来、日本人にとって神とはどのようなものだったのでしょうか。
「人々にとって、神さまはある時、突然、どこからかやって来るもの」でした。“まれびと”といってもいいと思います。菅野さんが指摘しているように「お客さまは神さまです」(演歌歌手三波春夫さんの言葉)ということになります。
でも、このお客さまは幸せを運んでくるだけではありません。“たたり”という脅威を与えることでその存在をしらしめることが多かったのです。ですからその怖れをさけるために“神”を祭ることが必要だったのです。
──わが国古来の神さまとのつき合い方は、客としてこられた神さまをもてなし、そのことによって豊かで平和な暮らしを得ようとすることであった。──
この自然信仰ともいえるものを神道として形を整えようとしたのが伊勢神道です。伊勢神道は日本書紀・古事記を意識して、独特な神話観(神観)を持って成立しました。菅野さんはまず伊勢の内宮と外宮の関係に着目します。「もともと外宮の方が先に伊勢の地に祭られており、後に大和政権の勢力拡大にともなって内宮がこの地に進出してきたのだといわれている」という説にふれて、
──律令の神祇制度では一応内宮の方が格上という扱いを受けていた。(略)しかし、中世以降明治に至るまで、幅広い階層の伊勢参宮の需要を満たして、経済的にも信仰的にも大きな力を持っていたのは、むしろ外宮のほうであった。伊勢神道の教説は、外宮の神職の間から生まれた。それは、このように、力はあるが格は下の外宮側が、自分たちの祭神の地位向上を意図して作り上げたものであるともいわれている。その真偽はともかく、最初の神道教説が、外宮の側から内宮を意識しつつ生みだされたという点は注目に値する。──
興味深いのは「格が下」ゆえに、かえって中心との一体化をはかったということです。周辺から出てきたものが、かえって(それゆえに)激しい中央志向を持つことになるということは、日本の歴史、思想史にしばしば見られます。
中央との一体化をはかった伊勢神道がもちいた論理が「同体異名説」です。この論理を用いることで日本書紀に記された神話世界、統治原理と矛盾しない、「いわば裏の筋立て」を作り上げることができたのです。この融通無碍さ、ある意味では牽強付会さともいうべき“神道”の特徴は伊勢神道以後も幾度も形を変えて現れてきます。このなにものをものみこむ神道の特徴(特性)が、習俗と宗教、国家イデオロギーとの区別を付けにくくさせ、習俗的なものと狂信的なものとの区別をしにくくしているのです。戦争の犠牲者が神と祭られることが持っている難しさがここにあります。実際、遺族の意思を無視して靖国に合祀されているということがあるということをどこかで読んだ気がします。
この不思議な入り口をもった神道の思想史に吉田兼倶(よしだ・かねとも)というカリスマが現れます。
──吉田兼倶の怪物たるゆえんは伊勢神道が保持していた二にして一という天皇と神道の微妙な一体性を踏み越えて、天皇の統治(王法)や、当時宗教界を支配していた仏教(仏法)に対する裏世界としての神道のあからさまな自立を宣言し、それを現実の行動においても実践してみせたという点にある。──
神道は吉田兼倶の出現によって大きく姿を変えました。彼によって神道は「仏教や儒教の理論体系とも通じ合う普遍的な真理を、捉え直そうとする」唯一無二のものとなりました。彼によって神道の融通無碍さはついに絶対的なものを証明する手段となったのです。習俗から離脱した思想・宗教の成立です。
この兼倶の神道は「明治維新に至るまで神道界に君臨する基礎」となったのです。山崎闇斎の垂加神道や本居宣長、平田篤胤の国学者の神道論にも大きな影をおとしました。
この本には多くの思想家、文学者が登場しますが、特に神国という観念を生んだ一人として北畠親房が取り上げられています。親房の『神皇正統記』は「大日本は神国なり」とかきだされていますが、これにふれて菅野さんは、
──神であるということを直ちに神聖なもの、優れたもののイメージに置き換えてしまうのは、日本の神のもつ奇(くす)しく異(あや)しい、底知れぬ豊かな奥行きを、痩せ枯れた抽象へとすり替えてしまうことになる。繰り返していうように、日本の神は真にして善なる超越者などという単純なものでは決してない。(略)神は私たちの日常の道徳の延長上にとらえることはできない。神国イコール他国に対する優越という理解には、神を道徳的な善なるものにみなそうとする近世・近代的な先入観が強く作用しているといわざるをえないのである。──
ここに菅野さんの公平さがあらわれています。神を神道というイデオロギーに吸収されることなく、日本人の自然へと取り戻すということなのでしょうか。これは、柳田國男、折口信夫、宮本常一たちの民俗学への道を取り戻すということです。逆にいえば、“自然の豊かさ”があるうちは神国イデオロギーと化さないものなのかもしれません。けれど“自然の喪失”が続く日本では“神観念”は抽象化・過激化することがありうるのです。そのことを踏まえた上でこの本を幾度も読み返してほしいと思います。読み応えのある1冊です。
レビュアー
編集者とデザイナーによる書籍レビュー・ユニット。
note
https://note.mu/nonakayukihiro
 レビュー
レビュー


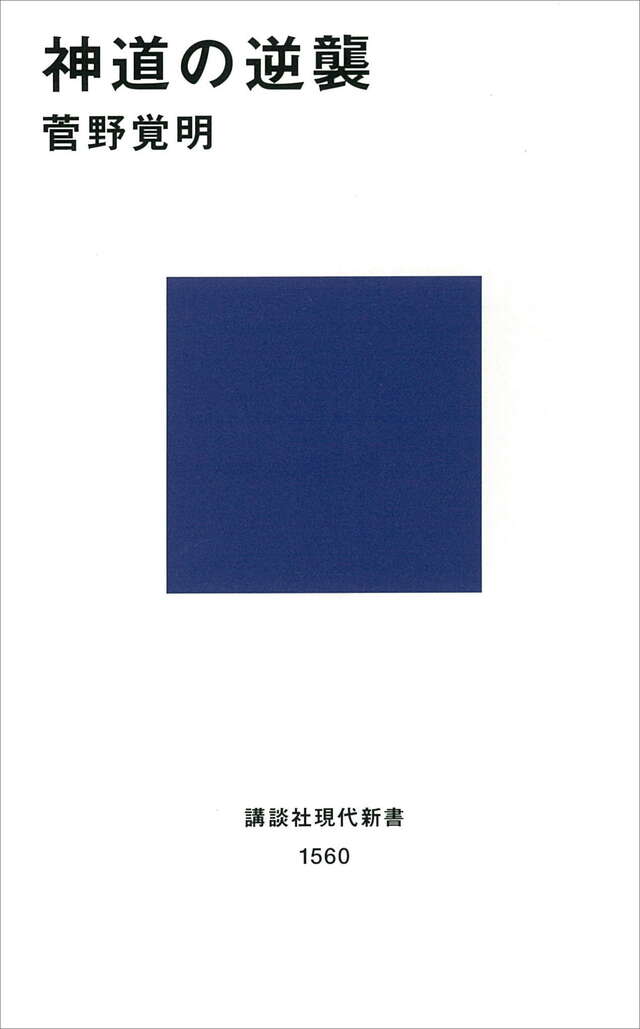





 特集
特集
