
これまで世の中に、働く女性のリアルな小説がなかった

こかじ さら
千葉県生まれ。中央大学大学院 国際会計研究科修士課程修了。出版社勤務を経て2010年よりフリーライターに。別名で執筆、編集に関わった著書は多数。本作品がデビュー作となる
──こかじさんは、ずっと編集者・ライターとして活動されてきていて、小説家としてはこれがデビュー作。いつかは小説を書きたいという思いがあったのでしょうか。
こかじ さら(以下こかじ):いえ、それが全く。書くきっかけとなったのは、昨年この作品の担当となる編集の今井さんと飲みながら、いろんな小説について雑談していたときですね。彼とは昔からの知り合いなんです。「そういえば、働く女性のリアルな小説ってあまりないよね」って私がふともらしたことがあって。女同士のいざこざや男女の暗部とか描いているのは読んだことあるけれど、現実の働いている女性って、ネチネチ、キャッキャしてるだけじゃなく、さっぱりしているところもあるし、案外真剣に仕事をやっているのにそういう小説がないんだよねって。そうしたら彼が「だったら自分で書けば」と。「書いたら読むよ」と言ってくれたものだからそれを真に受けて、じゃあちょっとやってみるかと短編を何本か書いて渡したんです。
──それまで経験なくて、簡単に小説が書けるものですか?
こかじ:小説ではないけれど、月に200~300ページぐらいの本の原稿をひと月で書くぐらいの仕事はずっとしてきたせいか、わりとすんなり書けましたね。今思うと、過去にも何度か「こかじ、小説書いてみたら?」と言われたことがあるんです。自分としては、ライター仕事の延長としてエッセイ的なことを書くこともあるかな、くらいは思ったことがありますが、小説は全く頭になくて。それが今回、なんだか言われてその気になったら書けてしまったという。最初は、働く女性を何人か登場させた連作短編集のように仕上がったんです。それを見せたら今井さんに、「うーん、いいけれどこういうスタイルは2作目とか3作目向きだな。デビュー作は、もう少しインパクトの強い方がいいよ」と言われ、その短編のなかのひとつに手を加えてふくらませたのが、この作品の原型。今井さんに送ったら、2、3日後に「おもしれぇ」って言ってもらえて。小説は頭の中だけでつくるものでしょ。書いた本人はおもしろいかどうかよくわからないから、人にそう言ってもらえたのは嬉しかったし、ありがたかったし、不思議な感じでしたね。
真剣に働いている女性とマラソンランナーに重なるところがある

──この作品『アレー! 行け、ニッポンの女たち』では東京マラソン、フランスのメドックマラソン、館山若潮マラソンと3つのフルマラソンレースのシーンが物語の大きな柱となっています。登場人物が全くの未経験から走ることに目覚め、挑戦する様子がこと細かく描かれていますし、こかじさん自身も日頃走っているということですが、「走る女性」を描きたいというのが最初にありましたか?
こかじ:最初から頭にあったのは、働く女性を描きたいってこと。世の中には頑張っている女性がたくさんいて、その人たちは、どんな試練があってもものともせずに踏ん張って生きる力強さがある。そんな元気な人たちの姿を描きたかったのがひとつ。私も四半世紀ほど会社勤めしていたので、そのとき感じたいろんな思いが経験として残っていてね。まっとうな人が救われる職場であってほしいというのが大いなる願いで、それを表現したいというのがあるんです。
私が走り始めたのは、この本の第1章と一緒で、東京マラソンに出る友人を応援しに行ったのがきっかけ。仲間と一緒に地下鉄を乗り継ぎながらコースをたどって声援送ってたら熱くなっちゃって。「踊る阿呆に見る阿呆」じゃないけど、ん? ただ見てるより向こう側の方がおもしろそうだぞ、走ったら自分はどうなるんだろうという気持ちがふくらんできて始めちゃったんです。実際に自分も走るようになって、ランナーの友人たちが、普段いかに走る時間をやりくりしつつ、きちんと仕事しているかということに気づきました。バリバリの銀行員で早朝出勤しているのに、退社後の夜10時から皇居で練習しているとか、毎朝5時起きで公園10キロ走ってプールで泳いでから出勤する役員レベルの人とか、市民ランナーの、生きる上でのモチベーションの高さみたいなものをものすごく感じたので、真剣に働く女性を描くときに、その伏線として走るってことが重なるんじゃないかと思って書いたんですよ。ランナーって、仕事だの家庭だのでいろいろ問題あったとしても、走るときは元気。この小説でもマラソンをからめたことで、登場人物たちが抱える深刻な悩みや不安を読者が共有しつつも、なんかちょっとスカッとするところもあり、救いになる部分も盛り込めたかなと。
──昔から、人生はよくマラソンに例えられますね。やはりそう思われます?
こかじ:この小説を読んでくれたある女性が、「静かに戦う姿が今の女性そのものね」って言ってたんです。「静かに戦う」って、マラソンもまさにそうで、他の競技みたいに相手とぶつかり合うものじゃなく、自分のなかでコツコツ練習してきたものを蓄え、本番でいかに上手く放出していくかなんですよね。すごくキツくて、あ、これもうリタイアかな、って思うわりには脚が動いていて、そうだよ、これだけ走り込んできたんだから大丈夫、まだいけるよ、とか走りながら実感することってあるんですよ。もうダメだって座り込んでシューズ脱いで、でもそこからまた気持ち切り替えて「よっしゃ!」って立ち上がってストレッチしてまた走り始めたり。そういうのって、仕事も同じで、長く勤めるうち無意識によいことも悪いことも経験として積み重なっていて、不条理なことが起きて傷ついても、案外自助的な癒し能力があるというか。傷つかない、倒れないんじゃなく、傷つくけど傷ついたら治せばいいし、倒れたら起き上がればいい、そんな風な強さが身につくんです。物語の後半では、応援の言葉を、意識して「頑張れ」でなく「踏ん張れ」としたんですよね。ただがむしゃらに頑張るっていうのでなく、どんなことがあっても下半身でグッと踏ん張ってる感じが、今の働く女性なのかな、と思って。その辺りも、勢いでなく体のコアを使って走るランナーに通ずるものがありますね。
リアルなセリフは自然に出てくるに任せて書いた
本の動画投稿コミュニティサイト「本TUBE」でこかじさんのインタビュー動画が見られます。
──登場人物たちのリアルなセリフのやり取りも印象的です。
友人のお姑さんがアプリ「小説マガジンエイジ」で連載中に読んでくれていたんですね。そしたら、ある日登場人物のひとりを指して友人に「これってあなたよね?」って言ったとか。彼女をモデルにはしてないんですよ。でも他の友人にも、「これって、私こかじに話したっけ?」と言われたこともあり、誰かしら思い当たる部分があるみたいで、リアルさを出したかった私としては嬉しい反応でしたね。セリフは考えるというより、自然に出てくるのに任せる感じで書きました。テレビとかで取り上げられるいわゆる「女子会」では、食べ物とか旅とか男女間のことばかり話してるように見えるけれど、そんなことなくて、日常時間の多くを会社で過ごしてる人なら、やっぱり仕事の話をしているんですよ。会社でこんなことがあった、今の仕事はこんな状況でさ、って。その辺もちゃんと描きたいと思いましたね。本の中のリストラにまつわる上司とのやり取りなんかは、覚えのある方には辛いシーンかも。私も勤めていた頃は、そりの合わない同僚や嫌な上司、いましたよ。その人たちを参考に、あいつならこんなふうに言うな、なんて思いながら書きましたね。復讐とかじゃないですよ。書く上では、やり返しません、恨みません、その代わりネタにさせていただきますってスタンス(笑)。ネタにするにしても、そっくりそのまま使えるわけじゃないから、そこが作家としての力量を問われるところだよな、と思いつつキーボードをたたいてました。とくに最後の方で嫌われ者の人事課の柳沢をどうするかは、結構悩んで。どうしたら読者が納得するか、今井さんとかなり話し合いましたね。これも、最終的にはマラソンシーンとからむことでお互いの心の揺れとかも上手く表現できたかな、とは思ってるんですが。
──今後も、働く女性の生き方を描いていかれるのでしょうか。
こかじ:ずっと先のことはわからないですが、今2作目をアプリで連載していて、こちらも働く女性が主役ですね。「ハイエナ女」という刺激的なタイトルなんですが、オフィスビルの清掃員として働く元商社社員だった50代女性の視点を中心に、会社組織の中の人々の思惑とか葛藤とか、いろんなものを浮き彫りにしつつ、でも希望につながるような、そんなストーリーにしたいなと。今井さんに、「四半世紀、企業で仕事して管理職まで経験した女性作家っていないんじゃないの? それ、かなり強みだよ」って言われて、そう言われてみればそうかなって。会社員時代のいろんなシーンが蓄積しているし、いろんな人にも会ってきているし。それを自分のなかから引き出しつつ、女性視点のね、仕事の物語はいくつか書きたいですね。「OL小説」なんてやわな感じでなく、ちゃんとした大人の女性の物語として。独身だったり、既婚でも子供がいたりいなかったり、シングルマザーだったり、病気を抱えていたり、家族の介護に奮闘していたりと、同じ組織のなかでもいろんな状況の女性がいるじゃない? その人たちが読んでホッとしたり、元気が出たり、属性に関わらず寄り添えるような小説が書けるといいなと思っています(談)。
取材・文:渡部響子
 インタビュー
インタビュー





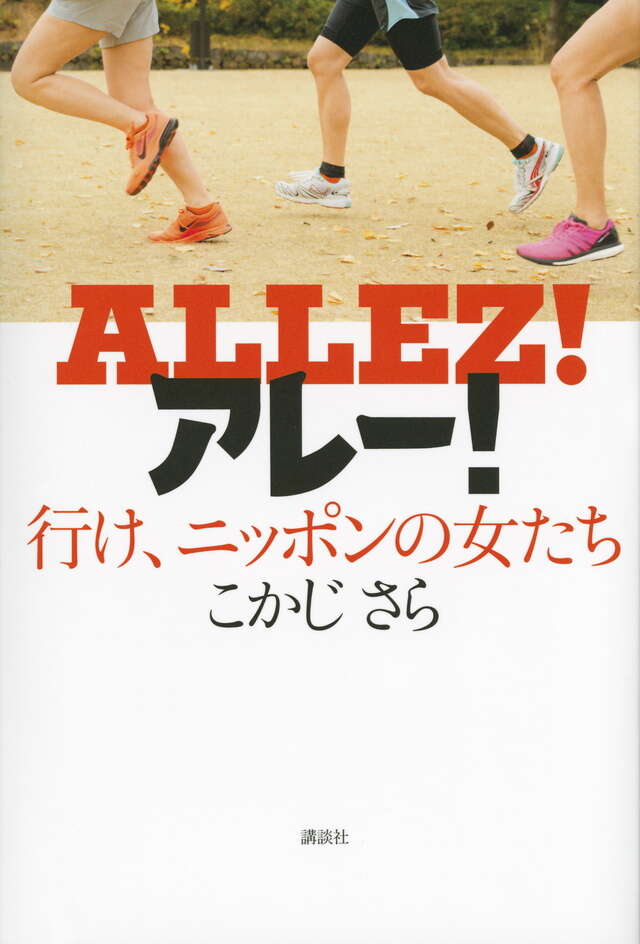

 レビュー
レビュー



 特集
特集
