
自分の好きなことで生計を立てることは、多くの人にとって夢である。ビジネスマンと小説家を兼業する新人作家、石川智健さんはそんな夢をかなえたひとりである。
医療系企業に勤めるかたわら小説を書き続け、日本・アメリカ・中国・韓国の出版社が共催する公募の文学賞、「ゴールデン・エレファント賞」に応募。2011年、『グレイメン』(エイ出版刊)で第2回ゴールデン・エレファント賞大賞を受賞し、小説家としてデビューする。現在も企業に勤務しながら積極的な執筆活動を続けている。「書くことは食事をすることと同じくらい自然なこと」と石川さん。毎日時間を決めてコツコツと書いているのだという。執筆速度はかなりのものだ。
そして2015年10月、5作目となる『60 tとfの境界線』(講談社刊)が発売された。今作の舞台は法廷、しかも冤罪がテーマである。
弁護士や法廷制度を取材した石川さんから、今回とても興味深いお話をうかがうことができた。

1985年神奈川県生まれ。25歳のときに書いた『グレイメン』で2011年に「ゴールデン・エレファント賞」第2回大賞を受賞。2012年に同作品が日米韓で刊行となり、26歳で作家デビューを果たす。『エウレカの確率 経済学捜査員 伏 見真守』は、経済学を絡めた斬新な警察小説として人気を博し、シリーズ最新作『エウレカの確率 経済学捜査員とナッシュ均衡の殺人』も好評を得る。その他に、警察の不祥事もみ消し工作を描いた『もみ消しはスピーディーに』がある。
Twitter:@i_tomotake
死刑判決の再審から見えた疑問。真実はひとつなのになぜ……


執筆時に使う資料は50冊以上。今回は法律や裁判に関する資料のほか、法曹関係者への取材や裁判の傍聴などを行い、物語のリアリティを追求していったという
──『エウレカの確率』シリーズでは経済学ミステリーというユニークなジャンルで人気が出ていますが、今作で法廷ものを書くことになったのはなぜでしょうか。
石川智健さん(以下、石川):いま勤めている会社の法務部に、仲の良い現役の弁護士の方がいるんです。同じフロアで働くようになってから、よく話をするようになったのですが、企業にいる弁護士はいったいどんな仕事をしているんだろうかと、とても興味が出てきたんですね。商標や著作権、敵対的買収の防衛など、そういったビジネスに特化した経歴を想像していたのですが、聞けば一般的な訴訟問題などを含めて民事や刑事まで、幅広い事件に携わった経験豊かな方だったんです。
その方からいろいろな話を聞くうちに、法廷ものに挑戦してみようと考えるようになりました。
──きっかけは、弁護士の視点だったということですね?
石川:そうです。取材も兼ねてさまざまな話を聞くようになり、それで、自分でも調べてみようと思い立って、弁護士会主催の講演会などにも足を運んでみたわけです。その中で特に印象的だったのが、死刑判決を受けたあとに再審が確定した方が出席された講演会でした。再審にまで至る報告会のような形でしたが、話を聞くうち、「真実はひとつなのにどうしてこんなに揉めるんだろう」と感じるようになり、裁判や死刑制度について調べるようになりました。
──そのときに、今作の土台ができあがったわけですね。
石川:ええ。ふだんの僕たちは刑法や裁判の制度など気にしないし、まして自分が刑事事件に巻き込まれるわけがないと思っていますよね。でも、なにかの拍子にそうした世界の当事者になることだってある。犯罪被害者になることはもちろん、逆に自分が犯していない罪で死刑判決を受けることがある。それが制度として成り立っているのに衝撃を受けまして、書いてみたいと思うようになりました。
──テーマの冤罪ということですね、取材も大変だったのではありませんか?
石川:資料や関係する職業の方々を当たるのはいつものことですが、いちばん影響を受けたのは裁判の傍聴です。東京地方裁判所に何度か傍聴しに行きましたが、傍聴席に身を置くことで法廷の空気を感じられたし、今回の作品に活かせたと思います。
──東京地方裁判所はどんな印象でした?
石川:霞ヶ関のとても高いオフィスビルのような建物なんですが、裁判所だっていう先入観があったので、見上げるととても威圧感を感じました。
残念ながら、安くておいしいと評判の地下の食堂には行けませんでしたが、代わりに弁護士会館の地下にある食堂に行きました。会社の弁護士についてきてもらったときに、なにかおいしいものをごちそうしなきゃと思っていたんですが、「鯛めし」があって。これがたしか2,500円くらいしたんですけど、とても美味しかったですよ。
──お昼に2,500円の「鯛めし」を食べる人なんているんですね。
石川:儲かっている弁護士は儲かっていますから(笑)。勝って「めでたい」的な験担ぎみたいなところもあるんじゃないでしょうか。
──どんな裁判をご覧になったんですか?
石川:薬物や詐欺などの比較的罪の軽いものから、殺人、強姦などの事件までさまざまです。ドラマや映画などで裁判のシーンはよく見てきましたが、あくまで画面の向こう側のフィクションとしか見ていなかったんですね。でも、傍聴席の目の前には、事件のせいで不幸に見舞われた人や、罪を犯したことでこれからの人生が決まってしまう人がいるわけです。空気や発せられる言葉のひとつひとつが重く、その人の気持ちに入り込んでしまうため、傍聴の前後は気分が落ち込んでしまうこともしばしばでした。
仲の良い弁護士さんに聞くと、感情はシャットアウトするようです。共鳴しないように、あえて無感動に、仕事と割り切ってこなすそうです。一見冷たいようですけど、それは結局依頼人のためでもあり、自分のためにもなるのだそうです。
弁護人の「異議あり!」はなし? 傍聴席から見た法廷は……

──なかなか裁判を見る機会がないので、法廷の中の様子を少し聞かせてください。
石川:裁判官と検事、弁護士の位置はみなさんドラマやニュース映像などでご覧になっているとおりですが、びっくりしたのは証人ですね。裁判官が「証人尋問を始めます」と言って証人の名前を呼ぶんですが、突然、傍聴席の僕の隣の席に座っていた人が立ち上がって歩いて行ったんですよ。「え!? なんで証人が傍聴席に座ってるの!?」みたいな。証人には顔を見られたくない場合もあるので、衝立で隠すなどの配慮がされることもあるのですが、普通は傍聴席に座っているみたいですね。
──検事や裁判官の印象はどうでしょう。
石川:見た目はさまざまでしたが、検事の方は目力がすごい!(笑)。裁判所内で「あ、この人、なんだか検事っぽいな」と思うと、やっぱり風呂敷を持っている!(※編注:検事は法廷に行く際に、書類や証拠品などを風呂敷に包んで持ち歩きます) 相手の罪を証明するのはたいへんストレスがかかる仕事ですから、眼光も鋭くなるでしょうし、ものすごく頭を使うでしょうし……、みんな頭よさそうでしたね(笑)。裁判官については、残念ながらあまり印象がないんですよね。いわゆる司会進行役ですから、個性を出す必要があまりないからでしょうか。
──弁護側はどんな印象でしたか?
石川:弁護人は、サラリーマン風の人もいれば、食わせものっぽい印象の人もいるし、やはりさまざまです。ふらついているような第一印象なのに、裁判が始まったらまくしたてるといった、本当にドラマに出てくるようなタイプの人もいました。また、弁護人は「異義あり!」と叫んだりするものだという世間の印象があるようですけど、そういうことはほとんど言わないみたいです。
──ええっ!? そうなんですか!? じゃあ「いまのは誘導尋問です!」とか「その質問は本件に関係がありません!」とかは?
石川:それもなかったですよ(笑)。僕が見た裁判は罪を犯したことを認めていて、あとはどういう量刑とするかが焦点でしたし、通常、どういう証拠品や資料が出てくるか、検事、弁護士双方が把握していますから、予定調和というのは言いすぎですけど、イレギュラーが少ないのかもしれませんね。
一方、予定調和的でなかったことで面白かったことが何度かありました。裁判官は閉廷前に被告人に「最後に言いたいことは?」とひと言を求めることが多いんですが、それを忘れて閉廷してしまったんですね。閉廷の後に「あ、すみません、今のナシ!」ってあわててやり直したことがありました。
延々心情を吐露し続ける被告人に裁判官が「そろそろやめてください」って、言ったこともありましたね。それでも延々しゃべり続けるので、とうとう検事が「次の事件が○号法廷であるので」と、風呂敷をまとめて法廷を出て行ってしまったこともありました。裁判長と被告人が雑談みたいに話すゆるい風景もありましたし、裁判もいろいろですね。
傍聴を通じて感じた裁判や刑罰の制度について

──傍聴に行った日に判決が出たようなことはありましたか?
石川:判決はありませんでしたが、1回目の冒頭陳述から始まった裁判を傍聴できたことがありました。検事が読み上げるんですが、ものすごく早口なんですよ。僕はまったく聞き取れなかったです。これが裁判員裁判の冒頭陳述となると、主張などがしっかり書かれた資料をスライドでじっくり見せていくんですけどね。誰が見ても分かるように丁寧に説明されているんです。
──傍聴を通して裁判に対する見方は変わりましたか?
石川:真実はひとつなのに、事件に対する検事、弁護士双方の異なる見解があって、互いにそれを主張する点が制度として興味深いと思いました。真実は当事者しか知り得ないことだから、裁判で他人がそれを的確に証明するのがとても難しいんです。だから、一方は断罪する側であり、もう一方は断罪される側を救う逆の立場で事件を追いかけていくわけです。また、真実の先には罪を償うためのさまざまな量刑が存在しますが、なかでも死刑は罪人の命であがなう方法で、取り返しがつかないこともあるはずです。死刑といった制度が正しいのかどうか、執筆中にずいぶん悩みましたし、いまも答えは出ていません。
──裁判の制度といえば、作中に起訴状などがそのまま登場しますよね。
石川:あれは実際に弁護士に起訴状を書いてもらって、それをアレンジしたんです。作中の裁判のシーンでも、実際の裁判での手順や手法をそのまま再現しています。書いたものは弁護士にすべて確認してもらいました。リアリティには徹底的にこだわりました。
次回作は弁護士もの! ファン待望のエウレカ3作目も確定

──今回、ずいぶんその弁護士の方に協力してもらったようですが、次回作の構想は?
石川:来年は、『エウレカの確率』の3作目が出る予定です。また、他社で弁護士ものを1本書こうと思っています。示談交渉を専門とする“法廷に行かない弁護士”というものです。あとは“弁護士ものの例のヤツ”を講談社で(※編注:これはヒミツだそうです)。できれば、日本で最初にやりたいと考えているので。弁護士ものは3作出したいと思っています。
──弁護士が旬なんですね。
石川:弁護士ものは面白いですよ。ますます面白くなってくると思います。弁護士って儲かっていると思うでしょうけど、いまは弁護士が儲かる時代ではなくなってしまっているんです。同業者が多いのももちろんですが、弁護士の中にはお金について強く言い出せない人もいるんです。依頼人の中にはあまりお金に余裕がない方もいるので、調査費などを弁護士のポケットマネーから出してしまう場合もあると聞きました。また最近では、弁護士が独自に捜査することも増えてきたようです。“捜査的弁護”というジャンルですかね。警察と同じような捜査をして、攻めの弁護をする。自分で現場に行って、関係者などから独自に証拠を入手して検察側の主張をひっくり返したり。これからの弁護士にはいろいろな役割が求められるようになるかもしれないと、知り合いの弁護士が言っていました。小説ではとても面白い演出ができそうです。
──ところで男性の場合、身近な冤罪に“痴漢冤罪”ってありますよね。
石川:僕には鉄壁の守りがありますから(笑)。やっぱり弁護士の知り合いは強いです。それと、最近では痴漢保険なるものがあるみたいですね。興味のある方は調べてみるといいですよ。
(聞き手:BOOK倶楽部)
 インタビュー
インタビュー


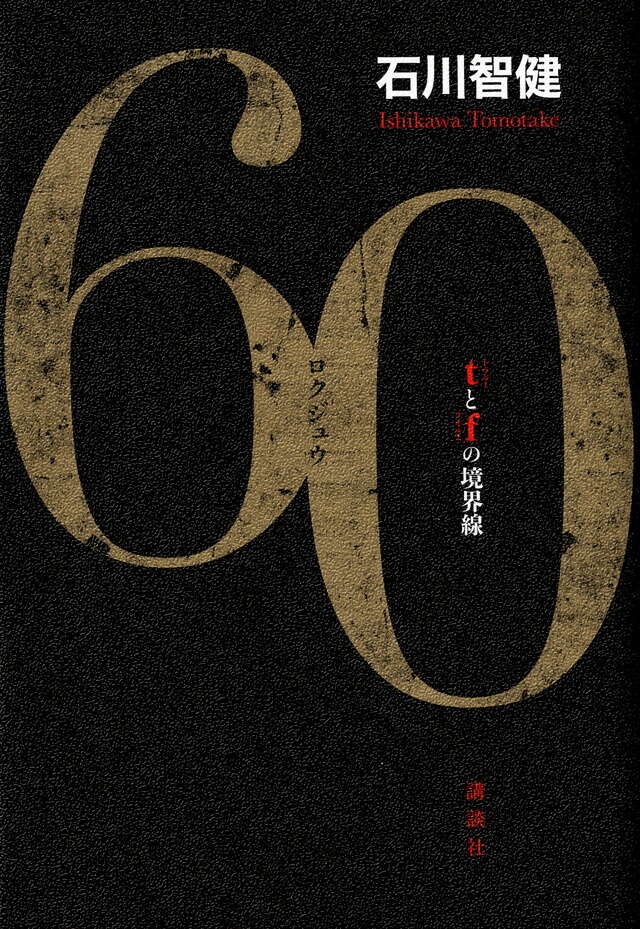

 レビュー
レビュー


 特集
特集

