「煮つめて取っておいたスープを、もう一度暖め直して飲むように、過去の歴史、伝統を、もう一度考え直して、現代に生かす新しい意味を知る」。
これが「温故知新」の言葉の著者による解釈です。これを、古きをたずねて新しきを知るというように紋切り型に意味だけをとると、大昔の聖人君子の教えでしかないというようになってしまいます。
貝塚さんがここで描き出した孔子はそんな石頭で偉そうな人間ではありません。優れた音楽を聴けば食事の味を忘れるほどの感動をうけるほどの情感豊かで、しかも弟子たちへの細やかな愛情にあふれた人なのです。
貝塚さんの描いた(想像した)孔子でしたら、いまの孔子廟を孔子本人が見たら赤面して避けるような人に違いありません。
もちろん貝塚さんは孔子を神聖視している儒学者ではありません。それどころか、『論語』の後半部では
「理屈ばっていてやや思い上がって激越な調子のものがふくまれて」
いるようで、貝塚さんはそこには「素朴で穏健で謙遜な」孔子らしさが見られなくなってるとも指摘しているのです。
「夢に周公を見ず」、と嘆じた孔子に習って言えば、後半の孔子は夢見ず、といったところなのでしょうか。
「朝に道を聞いても、夕べまで寿命がもつかどうか、将来をはかりがたいようなような世間」(朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり、の貝塚さんの解釈より)
という孔子の生きた戦乱の春秋時代とその後の戦国時代は諸子百家(儒家を始め、縦横家、法家、兵家、陰陽家、名家、道家などがいた)と称されるようなさまざまな思想家を生んだ時代でした。それが秦により統一され、やがて漢帝国の時代になると儒学が官学化され大いに儒教は尊ばれるようになります。
けれども反面では、学問が先人の教えの字義を解釈するというように狭められ、その解釈の正統化をのみ争うようになってもいったのです。いつの間にか孔子自身が持っていた融通無碍を失い硬直化していったともいえるかもしれません。そうして作られた偶像化された孔子のイメージの中から生きた孔子を救い出そうとしたのがこの本だと思います。
人類最大のベストセラーが『聖書』なら人類最長のロングセラーは『論語』ではないでしょうか。このロングセラーを作った男、孔子を知る最高の手がかりがこの本だと思います。
レビュアー
編集者とデザイナーによる覆面書籍レビュー・ユニット。日々喫茶店で珈琲啜りながら、読んだ本の話をしています。
 レビュー
レビュー


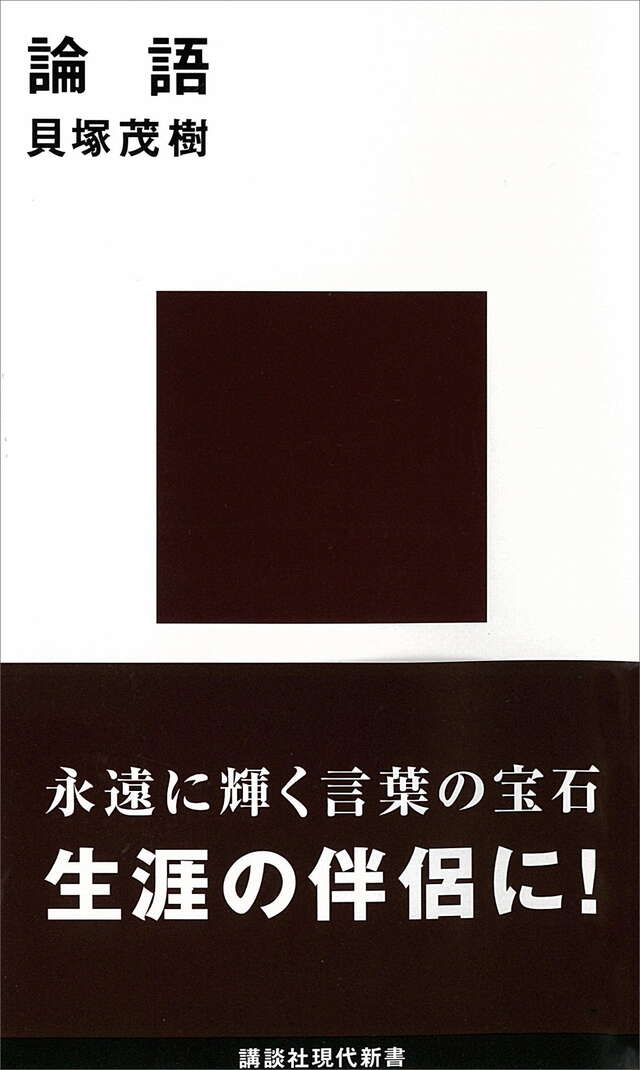




 特集
特集

